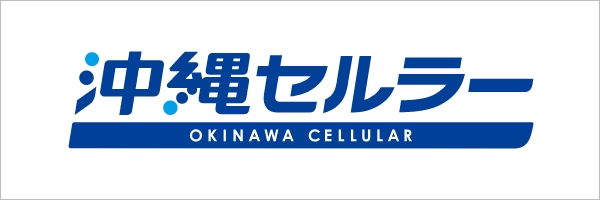「活き活きと暮らす人々の物語をなぞるように沖縄を歩く」今までになかったガイドブック、『新版 あたらしい沖縄旅行』
「活き活きと暮らす人々の物語をなぞるように沖縄を歩く」今までになかったガイドブック、『新版 あたらしい沖縄旅行』
Reading Material
買う
初回投稿日:2017.10.27
最終更新日:2024.04.12
最終更新日:2024.04.12
いつもより早く目が覚めて、カーテンを開けると、顔を出したばかりのぴかぴかの太陽の光を受けて、雨粒がキラキラ輝いている。何日も降り続いた雨が、嘘のように消え去って、どこからともなくやってきた小鳥たちが、木々の梢で夏がやってきた喜びを、体全体で表現している。

[撮影:セソコマサユキ]
人は時々どこか遠くへ行きたくなる。たとえば、新しい季節が巡ってくるとどこか遠くへ行きたくなる。一年に4度の季節の移り変わりが、心の中にある変化のスイッチを刺激するからだろうか。慣れ親しんできた何かが終わって、新しい何かが始まるまでのモラトリアムなひと時に、人は旅に出かけたくなる。誰かに出会って、何かに触れて、何かを感じると、新しいスイッチが入るのを知っているからだろうか。
そういう類いの旅は、観光とか、リゾートとか、そういうものとは少し違う。自分探しの旅ともどこか違う。新しくなるだろうことは決まっているけれど、どう変わるかは自分にもまだはっきりはわからない。身体の中になんとなくイメージがあるだけ。そういう旅は、何も描かれていない真っ白なキャンバスを抱えて出かけるような旅といえるかもしれない。

そんな旅におすすめなのが、今から4年前の夏に出版され、今年の夏に「新版」が出た『あたらしい沖縄旅行』だ。この本に登場するのは新しい暮らし方、新しい仕事を始めた45組の人々と、その人たちが営むお店、工房、クリエイティブなど。何が美味しいとか、どんなものを買えるとか、ガイドブックに欠かせないそういった情報の代わりに、満足そうに生きている人たちが何を考え何を感じているのかを通じて、沖縄の魅力を知ることができるという点で“あたらしい”ガイドブックなのだ。
パン屋さん、セレクトショップ、カフェ、本屋さん、焼菓子屋さん、ごはん屋さん、ケーキ屋さん、ドーナツ屋さん、やちむん工房、ガラス工房、器屋さん、カレー屋さんなどなど。著者のセソコマサユキさんが、旅行者として沖縄を訪れていた頃に出会った人や、生活の場を東京から沖縄に移そうと決めた後に新たに出会った方がこの本には登場する。

[撮影:セソコマサユキ]
「ガイドブックって表面的な情報にどうしても寄りがちじゃないですか。沖縄のお店を回るなかで、この人たちはなんで活き活きしているんだろう、なんで自由に生きているように見えるんだろうと、興味が湧いてきたんです。東京だとお店の人とお客さんの関係がビジネスの関係を超えることってそんなにないけど、沖縄だと、友人と友人の関係に発展していくことが結構あるんですよね」。
そのようなセソコさん自身の他者への興味を出発点に、思いがこもった仕事をしている人、仕事と暮らしがいい感じで重なっている人を、パーソナリティやストーリーを通じて紹介してあるから、よくあるガイドブックとは違うのだ。

読んでいると沖縄を旅してみたくなる。読み始めると沖縄で暮らしてみたくなる。そういう不思議な魅力が潜むこの本の着想が、いったいどこから生まれてきたのかをセソコさんに話を聞いてみた。
「神奈川で生まれ育って、東京で雑誌の仕事をしていた僕にとって、東京は雑誌編集という仕事の中心地だし、新しいものがどんどん生まれる場所でした。面白いと思える情報もここから発信されるわけですし、地方で暮らす意味をあまり感じていなかったんです。『自休自足』という雑誌の仕事で田舎を訪ねるようになるまではそう思っていました。でも、地方に取材に行って考えが変わったんですよ。出会う人がみんな活き活きしていたんです。今でもはっきり覚えているんですが、四国の今治にPaysanというパン屋があって、飛行機と船を乗り継いで、旅をするように文字通り、はるばる取材しに行ったんです。
オーナーが小屋を買って、自分の手でリフォームして作ったお店を、朝早くにお邪魔しました。そこでパンをこねる姿を目の当たりにしたわけですが、その姿があまりに生命力に満ち溢れていて…。朝日が当たってキラキラしてる光景がすごく印象的でした。生きるということに直球な感じに見えたんです。パンを焼くことと暮らすことがぴったり重なっていて、こういう生き方もあるんだとカルチャーショックを受けました。この本もそうですが、『あたらしい離島旅行』という続編や、その後に発売した『あたらしい移住のカタチ』という本も、実はPaysanのように東京時代につながった人にもう一度会いに行きたいという思いもあって生まれたんです」。都会から地方に移住したことがある人の多くが感じ考えることと、それほど遠くはないことをセソコさんも感じていたのだ。

[撮影:セソコマサユキ]
「消費される情報だとむなしいですよね。ガイドブックではありますけど、ここに書かれていることから人生をよりよく生きるヒントを受け取ってもらえるように、オーナーの生き方とか考え方を本の中に散りばめてみたんです。登場するのは力強く人生を歩んでいる人ばかりだから、読者のみなさんにも響くものがあるはずだと…。20年後に、たとえお店がなくなってしまったとしても、それでも読んでみて残るものがある。そういう仕事をしたつもりです。自分にはまだ小さい息子がいるんですが、彼が将来読んだときに、
『お父さんはちゃんとした仕事をしていたんだ』と思ってもらえるようにね」。
時間が経っても色あせないもの、いや、時間が経ってこそ色がより鮮やかに、より深くなるものがこの世には確かにある。そういったものは東京よりも沖縄などの地方の方により多いような気がする。

[撮影:セソコマサユキ]
「小学校5年生の頃、編集関係の仕事をしていた父からミヒャエル・エンデの本をもらって、文学の世界へのめり込んだんですよ。勉強も現代国語だけは好きでした。そういうふうに出版業界に入って、30歳くらいまでは才能ある人と一緒に東京で仕事ができて楽しかったですよ。成長する自分も見えるし。でも、34歳くらいから時間の価値が変わってきたんです。寝るために家に帰るような生活でしたから。『ずーっとこのままでいいのかな』って。暮らすことにしっかり目を向けたいなって」。
家族ができたのが大きな転機だったとセソコさんは振り返る。
「暮らすことが仕事であって、仕事が暮らしである。それが実現できるのが沖縄だと思って移住をすることに決めました」。

[撮影:セソコマサユキ]
生活の豊かさをはかる一つのものさしは、自分の生活をどれだけ他者と共有できているかということではないかと、移住してみて時々思う。仕事であっても、暮らしであっても、他者とすーっと繋がれて、公と私の境界がいい意味で曖昧なのが、沖縄をはじめとする地方の特徴の一つではないだろうか。そこでは、オンとオフの区切られ方が、都会とはたぶん違うのだ。
実はセソコさんは、名前が示す通り、沖縄の血を引いている。そのことも、新しい暮らしと仕事を選び取る時、影響したのだろうか。
「初めての沖縄旅行は家族旅行でした。中学校1年生でしたね。本島南部にルーツがあるんです」。
返ってきた言葉は、どこか淡々としている。その後も1人旅、2人旅で沖縄を旅し続けたというセソコさんに、実際に暮らしてみてからの印象の変化について訊いてみた。

「初めての旅したときから沖縄に“南国リゾート”を期待していたわけではないんです。だからそういう意味での色あせた感じはありません。言えるのは、暮らしはじめてからも人に魅了され続けているということです」。
旅行者として通っている間は、非日常感からくる気分の高揚もあって、沖縄の光の部分が眩しく見えても、移住してみると、非日常が日常に変化していくにつれ、かつてのリゾート感は色あせて、光よりも影の部分が強烈になることがあるらしい。でも、セソコさんの場合は、違うようだ。
「この本で沖縄での人間関係の大きな枠ができたんです」。
旅していた時も、暮らしてみてからも、変わることなく魅力的であり続ける沖縄が、誇らしくあるのだろうか。いつも涼しげなポーカーフェイスのセソコさんが見せた、子どものような笑顔が、この本が伝えようとしているものを示しているように見えた。
『新版 あたらしい沖縄旅行』
出版/WAVE出版
![]() 沖縄CLIP編集部
沖縄CLIP編集部