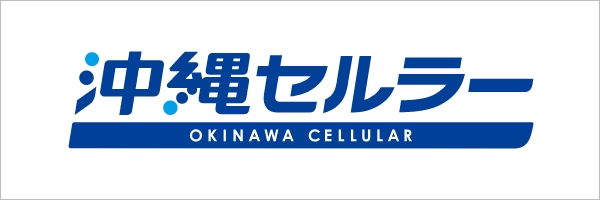沖縄の木々から生まれたアクセサリーと暮らしの道具たち
沖縄の木々から生まれたアクセサリーと暮らしの道具たち
Reading Material
歴史文化
初回投稿日:2018.04.23
最終更新日:2024.05.17
最終更新日:2024.05.17



「木地はなんだかわかりますか?」。サイケデリックで妖艶な輝きを放つペンダントを手にした工房ぬりトンの森田哲也さんが言った。持ってみるととっても軽い、そして、羽根のように薄い。答は麻布。奈良時代に中国から伝わった乾漆と呼ばれる技法で作ったものだという。麻の布に漆を塗って、また麻の布を貼って漆を塗って。漆と布で貼り重ねたものだから、軽いし整形も比較的自由にできる。その上にアワビ貝を磨いて真珠のように光る薄片をあしらって完成。こちらも奈良時代に中国から伝えられた螺鈿(らでん)と呼ばれる技法だ。何も知らない状態でこのペンダントトップを目にしたら、奈良時代からの技法が使われているとは想像できなかったかもしれない。

こちらのホエールテールのような形に見えるペンダントは寒緋桜の材を使って、寒緋桜の花びらを象ったものだ。艶やかな朱色が印象的なモード系のシリーズ同様、こちらも古くからの漆芸の技術によって作られている。テイストやデザインこそ漆器のイメージからいい意味で離れてはいるけれど、先輩の手から手へと、長い年月をかけて受け継がれてきた伝統的な技が、アクセサリーの一つ一つに、今という時代に合わせて咲いているようだ。
意外にも前職は水質管理のプラントエンジニアだったという哲也さん。あるとき、漆器の産地、輪島市にある石川県漆芸美術館を訪れて、蒔絵を目にして漆器の虜になった。さっそく地元の蒔絵教室に通い始め、しだいに漆を箆(へら)や刷毛で素地に塗るという、?漆(きゅうしつ)の技術を本格的に学びたくなって、沖縄に移住。本島南部の南風原町(はえばるちょう)にある工芸指導所(今の工芸振興センター)で漆芸を学んだ。そのとき知り合ったのが、パートナーの敦子さんだという。


木肌が素朴な美しさとして現れている器やカトラリーは敦子さんが作ったものだ。敦子さんは、東京の美術大学で木工を専攻し、卒業後は知育玩具やおもちゃを製造するメーカーに就職。そこで、デザイナーとして働いた。5年半ほど愛知県の木工房で修行をして、生活に密着したものを作りたいと思うようになったという。食器には身体にも無害でしかも丈夫な世界最強の天然塗料といわれる漆に惹かれるようになり、漆芸の門を叩いたのが沖縄だった。

「昔は図面に合わせて作っていたんですけど、今は素材を見て、そこから何を作るかを決めてます。沖縄は台風も多いし、島だから風が強い日が結構あるんです。木は倒れないように必死に踏ん張るじゃないですか。だから、曲がったりねじれたりした材になるんですね。おおらかさというか、テーゲーさというか、そういう個性は、樹齢何百年という柾目(まさめ)の銘木(めいぼく)とは違った別の価値があると思うんです。時間が経つと反ったり動いたりしやすい材は、動きを活かしてあげるような曲線的なデザインに仕上げたりします。まだまだ、つかめきれない部分はありますが、木が持っている個性を活かせるように作っています」。
沖縄では馴染み深いクワズイモの葉っぱを象ったお皿や、丸みや厚みを活かしたお菓子入れが敦子さんのものづくりの姿勢を語っている。材料を人間に合わせるのではなく、人間の方が材料の特性に合わせたもの作りをすることで、その土地らしさが引き出され、風土やストーリーを映し出すものができあがる。




もちろん、丸いもの、厚みのあるものばかりを作っているわけではない。作り手としての感性や、使い手のニーズもあるから、箱物(指物)なども作っている。反ったり割れたりすることなく、真っ直ぐでないと機能を満たさないものには、タモやケヤキなどの県外や国外の材を使うこともある。
それでもやっぱり、好きなのは沖縄の木だそうだ。「木によって好きな理由がそれぞれある」と敦子さんは言う。「本土の松とは違って色白な琉球松は、脂分が多くてしっとりしているんです。赤っぽい風合いと落ち着いた印象のタブは、触れたときの質感が心地よいし、寒緋桜は硬すぎず柔らかすぎす、薄く仕上げても割れにくい。加工するときに刃がしゅっと入るし、桜の香りがして気持ちがいいんです。ほら、桜餅の香りがするでしょう」。差し出されたお皿に鼻先を近づけると、なるほど桜の葉の香りがほんのり漂ってきた。

「これはセンダンです。濃くて大きな道管が目立っていて模様みたいでしょう。大胆な木肌が南国っぽくて好きなんです」。楕円形の大きなお皿を手にした敦子さんが顔をほころばせる。「触ってると癒されますね。反ったり割れたり、思い通りにはいかないことも多いですが、でもそれは自然のものだからあたりまえで、人間の手に負えない厳しさや難しさがかえって面白いです。『完成した!』と思ったら割れたり反ったりすることもあって、よく泣かされてますけどね」。木工の魅力を尋ねるとこんな答が返ってきた。


「素材として人の肌に近い気がしますし、温もりがありますよね。削っていても楽しいし、木目が何より好きなんです。切られたのに、生きてるように感じられるし、製材して板にしただけでも美しいじゃないですか。木によって個性があるのがまたいいんです。同じ樹種でも育ち方が木目に現れているところもね」。木に対する思いを熱く語る哲也さんが、同じサイズの木の見本板を差し出してくれた。手にとると、重さが違うし、磨いてあるのに手触りも違う。



哲也さんは工芸指導所を卒業してしばらくして、首里城の修復の仕事に関わり始めた。漆の塗り直しを通じて、先輩の漆芸家や学芸員など、畑違いの専門家との交流が始まった。今まで知らなかった世界が目の前に広がったことで、改めて漆にのめり込むようになった。
「首里城が建造された当時の技法は書物には残っていないんです。漆にどんな素材を混ぜてあの色が作り出されたのかは、科学分析することでようやく明らかになっていく。そういう未知との遭遇によって、『琉球漆器とは何だろう』と、沖縄の漆芸の独自性に目が向き始めました」。
それからは、赤瓦を砕いたものを漆に混ぜた「赤瓦の地の粉」を自分なりに試作したり、ニービと呼ばれる琉球砂岩を混ぜた下地に白漆を塗り重ねたオリジナルの器に取り組んでいる。木地に漆を塗ったあと、ニービ下地を付けて人差し指でらせん状になぞる。そこに白漆を塗る。やちむん(沖縄の陶器)で時々見られる人の指の痕跡は、それが人の手によって作られたことを教えてくれる。それを漆器に応用したいと、森田さんが考えた技法だ。
漆器や和紙などの工芸品では、職人が技術を極めていけばいくほど、できあがったものには、1ミリの違いもない見事なまでの均質さと、つるりとした質感が備わってくる。一流を目指すと、人の手の痕跡が結果的に薄れていくが、森田さんの取り組みには、人の手の痕跡をあえて再現することで、新しい漆の世界に切り拓いていきたいという思いがあるのだろう。


取材の最後に敦子さんが皿を彫り出す工程を見せてくれた。「彫るのと同じくらいの時間、刃物を研いでるんですよ。刃の研ぎ方で仕上がりが変わるんです」と、敦子さんは鑿(のみ)をシュッシュと手際よく動かしながら教えてくれた。上手に木を彫るのに必要なのは腕力ではなくて、よく手入れされた道具だという。「実は、漆を塗っている時間よりも塗った後に磨く時間の方が長いんですよ。だいたい3:7くらいですかね」と、哲也さんも言葉を重ねた。そのような、人の目に触れることのない見えない時間が、一つのものが完成するまでに、たくさん隠されているということだろう。
「今は、それぞれで自分が作りたいものを作っていますが、これからは、ふたりでデザインを考えて、ゼロから作って仕上げていきたいです。喧嘩になるときもあるかもしれませんが、それも含めてのものづくりですからね」。今後は琉球松を作った家具も作っていきたいという、ふたりの森田さん。コラボレーションから生まれる木のもののから、どんな手触りを感じがることができるだろう。
◎工房ぬりトンのアクセサリーや器は以下のお店で購入できます。(2024年5月現在)
・フラッグシップOKINAWA
・しびらんか
・tituti OKINAWAN CRAFT
・ギャラリーはらいそ 識名店
・ギャラリー泰山
・りゅう
工房 ぬりトン
- 住所 /
- 沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座834-2
- サイト /
- https://nuriton.jimdofree.com/
![]() 沖縄CLIP編集部
沖縄CLIP編集部
- 前の記事 伝統工芸とポップカルチャーのコラボレーションが紅型の新しい可能性を切り拓く
- 次の記事 「Okinawa」の食やお酒を新しい解釈で提案するB&B+カフェ『La Passione(ラ・パッショーネ)』