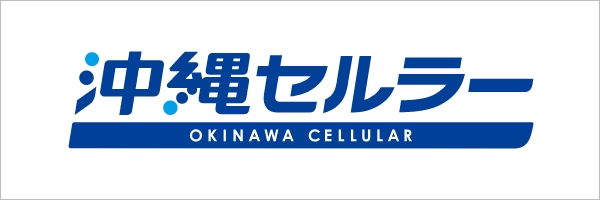りんけんバンドのリーダーに聞く――照屋林賢と、沖縄。(後編)
りんけんバンドのリーダーに聞く――照屋林賢と、沖縄。(後編)
Reading Material
歴史文化
初回投稿日:2021.12.30
最終更新日:2024.05.23
最終更新日:2024.05.23
目次
ウチナーグチ(沖縄方言)の歌詞、沖縄の音階とリズムをベースに、洋楽を取り入れるスタイルで、1977年に結成されたりんけんバンド。
ここでは、約45年という長い活動歴を辿り、沖縄でこの音楽が生まれた源流を探るべく、リーダーの照屋林賢(てるやりんけん)にインタビュー。2回に渡る特集記事の後編では、25歳の照屋林賢が東京から沖縄に戻ってからの話をお届けする。
(前編)の記事はこちら

自社スタジオにてインタビュー時の照屋林賢。三線とギターを合体させた楽器「チェレン」と。
知名定男のバックバンドとしてスタートしたりんけんバンド
本土復帰から2年経った1974年、25歳の照屋林賢(てるやりんけん)は、音楽を学ぶため出かけた東京での生活に区切りをつけ、沖縄に戻った。
その後、ジャズバンドでベースを弾いたり、地元コザの店で民謡や洋楽クラシックのギターソロ演奏をしたり、各所でライブ活動を続けていた1978年のこと。沖縄民謡と洋楽を融合したアルバム「赤花」で全国デビューを飾ったばかりの知名定男から、「自分の唄三線のバックで演奏するバンドを作ってほしい」と依頼を受ける。そこで、林賢がベースを担当し、ギター、ドラムス、キーボードという4人編成のバンドを結成。これがりんけんバンドの原点、すべての始まりだった。
「りんけんバンドという名前は、定男さんが決めてくれました。三線一本では細いサウンドが、バンドでやると大きく派手なサウンドになる。それが楽しくて、沖縄中あちこち一緒に回りましたね。だけどあるとき、ライブの中盤に定男さんが一人で三線を弾いて歌うコーナーを作ろうということになって。僕らバンドメンバーは、その間休んで袖から見ていたんですが、聞いているうちに気づいたんです。僕らのバンドサウンドは、定男さんの三線一本のサウンドに負けているなって。これはだめだってひどく落ち込みました。それで、定男さんの三線一本に勝てるバンドを作りたいと言って、バックバンドを辞めさせてもらうことにしたんです。定男さんは僕にとって大事な師匠。だからこれは、定男さんから離れるということではない、定男さんから生まれたんだと思いました。何かから何かが生まれて継いでいくということなんだ、と。それで、りんけんバンド第2のスタートを踏み出すことにしました」

1991年頃の照屋林賢/写真提供:アジマァ
半径5メートルの隣近所に「いいね」と言われる音楽を目指して
独立後は、ヴォーカル、三線などのメンバーを加え、新たな編成に。歌詞は、すべてウチナーグチで作る。サウンドは沖縄の音楽をベースに洋楽を取り入れる。そうしたスタイルで、りんけんバンドが単独演奏するようになったのが1980年ころ。ライブをする機会はあった。けれど、観客に受け入れられない、認められないという寂しい体験が続いた。当時「ポプコン」の通称で注目を集めていた音楽コンテスト「ポピュラー・ソング・コンサート」では、沖縄代表に選ばれ、3度も大阪大会に出場したが、そのたびに冷たい反応を受け、全国大会には進めなかった。地元コザで開催された「ピースフル・ラブ・ロック・フェスティバル」では、ブーイングの嵐。「帰れ」コールを受け、悔しい思いをした。
「内地で受けない、アメリカ人に受けない。最初は腹が立ったけど、ゆくゆくは価値の違いだからどうしようもないなと思うようになりました。でも、ウチナーンチュ(沖縄の人)までブーイングするのには本当に腹が立った。自分たちが生まれた沖縄の音楽をやっているのになぜ応援してくれないのか、と。いったい僕たちはどこを目指して音楽をやればいいのか悩みましたね。そんなとき、知り合いの子供が僕たちの歌をカセットで聞いて、ずいぶん気に入ったらしいと聞いてね。毎朝起きると必ず『聞かせて』とせがむらしいんです。これが本当に嬉しくてね。あぁ、半径5メートル以内の隣近所の人たちが『りんけんバンドいいね』って言ってくれたら上出来だなって。広い世界で受け入れられなくても、沖縄で自分たちが本当にやりたいことをやろう。小さな種を植えていって、一本でもいいからしっかり育てていこう。そう心に決めました」

りんけんバンド南米公演の様子/写真提供:アジマァ
沖縄の音楽を取り入れているのではない。沖縄の音楽がベースだ
そんなりんけんバンドが注目され始めたのは1985年。「沖縄の新しいお祝いの歌を作りたい」という思いで生み出した楽曲「ありがとう」が、オリオンビールのCMソングに起用されたのがきっかけだった。
「タイトルはウチナーグチではないけれど、これにはちゃんと狙いがありました。沖縄の歌には『アリ』という囃子言葉があるから、これを『アリッ! アリッ!』とまず歌って、聞いている人が囃子だと思ったところで、『ありがとう』と続けたらウケるんじゃないかなと(笑)」
そうした狙いが当たったのか、「ありがとう」は人気を博し、1987年、本作をタイトル曲に掲げたファースト・アルバムのカセットをマルテル・レコードより発表する。1990年にはCD化され、全国リリースへ。東京と大阪で発売記念ライブを開催するなど、沖縄以外の地でもその存在が広く知れ渡ることになった。セカンド・アルバム「なんくる」発表後は、全国ツアーを敢行。イギリス、フランス、アメリカなど海外イベントにも出演するようになり、りんけんバンドの音楽は、海を越え多くの人の耳に届けられていく。
「沖縄以外でも受け入れられたっていうできごとは嬉しかったけど、当時はそこまで深く考えていなかったですね。ただただ音楽を作ることが楽しくて、メロディーをあれこれ構想してみたり、三線はこんなふうに弾いたらおもしろいんじゃないかとか、そんなことばっかり考えていました。自分が作った音楽をバンドで再現できるという喜びが一番だったんですね。逆にショックだったのは、新聞や雑誌の取材で『沖縄の言葉、三線、踊りを取り入れているんですね』と言われたこと。逆です。りんけんバンドは、沖縄の音楽をベースに洋楽を取り入れている。そこが一番大事なところなのにっていつも悔しい思いをしていました」


フランス公演時の様子/写真提供:アジマァ
外の世界から眺めて気づいた、沖縄の美しさ
数々の海外イベントに出演し、ライブを成功させてきた功績についても、こう語る。
「周りのみんなは『沖縄の音楽が海外でウケた』とか騒いでいたけど、果たして外からやって来た僕たちの音楽が本当にウケたのかな?と。どの国にも、その土地の音楽がある。自分たちの生まれた土地の言葉を使って、これが自分たちの音楽だって胸を張って活動している人がいる。沖縄でいう僕みたいな人間が、世界中それぞれの土地にいるんですよね。それこそが素晴らしいことじゃないか、と。僕が海外に行って何がよかったというと、そういう地元で頑張っている人たちと出会えたこと。それによって、自分の立ち位置がわかってきたんです。音楽との出会いというものは、自分がいかに大事か、周りの人たちがいかに大事か、それに気づくことと関係している。音楽が持っている本当の力って、そういうもの。りんけんバンドはそれを感じさせる音楽を作らないといけないと思うようになりました」
10代後半から経験した東京生活や、海外での公演。沖縄から出て、外の世界を体験するということ。それによって自らを見つめ直し、大切にしたい音楽に気づかされてきた。そして、生まれ育った沖縄の本当の美しさのことも。
「東京で灰色の海を見たとき、びっくりして。沖縄の海がいかにきれいなのか初めて知りました。生まれたときからただそこにあって、なんとも思ってなかったものが、どれだけ素晴らしいものなのか、沖縄の底知れぬ良さに気づいたんですね。それは、知名定男さんと一緒にやっていたときに習った感覚的なものにも通じるし、琉球古典音楽の世界、古いメロディーにも感じることです。僕は東京から沖縄に戻って、野村流の琉球古典音楽家、島袋正雄(しまぶくろまさお)先生のもとへ古典を習いに行っていたんですね。定男さんと、東京でお世話になったピアニストの玉栄政昭(たまえまさあき)さんと3人で一緒に通っていたんです。島袋先生は本当に素晴らしい方でね。先生の唄を残したい、みんなに伝えたいという思いで、僕が録音したカセットをマルテル・レコードから発売しました。『野村流の工工四(楽譜)全巻をそのままの通り歌う』という企画で、10年以上かけて完成させたもの。レコーディングの現場で、先生の唄三線を聞くたび、ほかの誰にも真似できないものすごく美しいものを目の当たりにするようで、いつも感激していましたね。こんなふうに一本の旋律で相手を感動させられるような、独自の美を求めることが大事なんだと気づかされました」

写真提供:照屋林賢
「身の回りにある物語」に気づくことから始まる作詞の世界
りんけんバンドの歌を聞くと、沖縄のことがよくわかる。海や花のこと、エイサーや大綱曳など行事のこと、肝心(ちむぐくる)や志情(しなさき)といった人の心のあたたかさのこと。林賢は、「物語は常に身の回りにある」と言う。それに気づくか気づかないか。歌を作るということはそういうことである、と。
「僕は夕陽の写真が好きで、20年くらいずっと撮っているんです。夕陽を見ている人たちを眺めながら、みんなきっと感動しているんだろうなとか想像したりしてね。あるときふと思ったんです。アーティストたちは、きっとこの夕陽の感動を形で表現するだろうって。絵描きだったら描き、作曲家だったら曲を作り、歌手だったら歌う。じゃあアーティストではない人の感動はどこにいくのだろうか。疑問に思いました。でも、そういう人たちも自分が気づかないだけで、心の中でメロディーが鳴っていたり、絵を描いているのかもしれない。結論的にみんなが芸術家なんだなと思うようになったんです。そういう意味では、僕にとっても詩を書くということは特別なことではないと思っている。そのあたりをぱっと見たときに『詩がある』という感覚なんですよね」

父・照屋林助(左)と林賢/写真提供:アジマァ
1992年の発表時から歌い継がれるりんけんバンドの名曲「黄金三星(くがにみちぶし)」は、父・照屋林助が作詞を手掛けている。
「僕には、師匠が4人いるんです。民謡唄者の知名定男さん、ピアニストの玉栄政昭さん、琉球古典音楽家の島袋正雄さん、そして父の林助。林助とはいつも喧嘩ばかりしていたけれど、『黄金三星』の歌詞を読んだときは、これはもう頭が上がらないと感じましたね」
本曲は、林賢が劇中音楽を担当した1992年公開の映画「パイナップル・ツアーズ」のエンディングテーマとなっている。林助に作詞を依頼、作曲を自身が手掛けるという親子タッグの作品だった。
「映画の撮影地の伊是名島(いぜなじま)に出かけて、そこで感じたことを物語にして林助に渡し、これで詩を作ってくれとお願いしました。『島には、あるおばあさんが一人で暮らしていた。外からたくさんの人が入ってきては出て行って、島は変わっていくけれど、おばあさんは何も変わらず島から一歩も出ることなく暮らしていた。1年に1度、山の丘に上がって空を見上げる。毎年、天の同じ位置に星が帰ってきて止まる。それを見て、おばあさんは今年も島は安泰だと幸せを感じる』。そんな物語でした。その後、林助から歌詞があがってきましたが、僕は2度ボツにしました。林助は、ものすごく怒っていたけど『違う』と突き返した。それで3度目にあがってきたものが、驚くほどよかったんですね。メロディーが浮かんできて、すぐに曲ができあがった。林助もすごく喜んでいましたね」
受け継いでほしい、小さな島の足元から育っていく音楽
りんけんバンドは、そうした数々の名曲を生み出しながら、現在は、北谷町美浜(ちゃたんちょうみはま)のアメリカンヴィレッジにあるライブハウス「カラハーイ」を拠点に活動を続けている。レコーディングスタジオ「アジマァ」、沖縄料理が楽しめるレストラン「リンケンズキッチン」、オーシャンビューが魅力的な「リンケンズホテル」が一体化したエンターテイメント感あふれる空間だ。

リンケンズホテル、リンケンズキッチン、カラハーイの外観/写真提供:アジマァ

リンケンズキッチンの料理/写真提供:アジマァ
取材で訪れたとき、「カラハーイ」は休業中で、無観客の配信ライブが行われていた。林賢がプロデュースする女性4人組、ティンクティンクがメイン出演する番組で、この日は、りんけんバンドのヴォーカルで林賢の妻である上原知子もゲスト出演していた。ふと見ると、映像を撮影するカメラマンも、音響機材を操るPAエンジニアも、照屋林賢が一人で担っている。思わず「すごいですね」と声をかけると、「適当にやってます」との返事。そういえば、取材中笑いながら口にする「適当」という言葉の響きが、やけに心地よかった。


「僕は、ライブをやる前にメンバーに『適当にやろう』と言うんです。力まず、リラックスして楽しもうということですね。音楽ってそういうものだと思う。この配信も、最初はどう表現したらいいかな、みんなはどう思うかなと価値を求めていたところがあって、迷っていたけれど、途中から『適当にやるしかない』と思うようになりました。多くの人に支持してもらうためにやるのではなく、自分たちがやりたいことを発信することが大事じゃないかと。ティンクティンクの4人はまだ若いから評価がとっても気になると思うけど、僕は気にするなと言っています。自分の歌を一人でも好きでいてくれたら、これでいいんじゃないの、と。彼女たちには、もっと自分自身を深く知り、生まれた沖縄の地のことを学び、足元にあるものを育てていくことが大事だと話しています。そうすることで、地面から出てくる栄養が発想につながり、表現が生まれ、音楽になっていく。自分が大切にしてきたそういうものを4人に受け継いでいってほしいと思っています」

上原知子、ティンクティンク、照屋林賢
スタジオの隣にある事務所で、「FUNAYARE Orchestra Version」のミュージックビデオを一緒に鑑賞した。船出する人と残る人との別れを綴った1991年発表曲「ふなやれ」を、2020年、新たに日本人オーケストラとの共演で録音したものだという。映像は、ここでもなんでも一人でこなす照屋林賢が、撮影、編集を担当。ドローン撮影によって映し出される沖縄の海の景色は、息をのむほどに美しく、壮大なハーモニーと上原知子のヴォーカルとの愛あふれる響き合いはどこまでも優しく、胸が震えた。かつて沖縄の人たちが、船に乗りさまざまな思いを運んだ歴史を思うと、こみ上げるものがあった。
「実はこれ、チェコ・プラハのオーケストラと共演しようと、5年前から構想していた企画だったんです。いざ実現しようとしたとき、ちょうどコロナで海外に出かけられなくなったから、まずは日本人オーケストラとやってみようと試みたのが今回の作品。僕は、オーケストラっていうのは、国籍とか人種とか何もかも超えて、もはや人類のハーモニーだと思っているんです。それに比べて沖縄の言葉というものは、日本という小さな島国の中の、そのまた本当に小さな島の言葉。そんな針の先のような島の言葉と、人類のハーモニーが融合する音楽を作ってみたかった。沖縄の音楽をベースに、もっともっといろんなことができるんじゃないか。そんな希望が今、僕の中にあふれているんですよね」

上原知子と照屋林賢
「ウチナーンチュという自覚はある。でもそこに縛られるつもりはない」という自由な発想を抱きつつ、足元に息づく小さな島の輝きを大切に奏でてきた照屋林賢。彼が語った夕陽の話を思い出しながら、「カラハーイ」の近くにあるサンセットビーチを訪れると、美しい夕景が広がっていた。沖縄の美しさを宿したりんけんバンドの音楽は、こういうところから生まれてきたのだなと夕陽と重ね合わせて考えた。そして今、林賢の中にあふれる希望が、どんな音楽に結実していくのか。これからも長く続くだろうりんけんバンドの音の旅が、ますます楽しみになった。
【参考図書】
照屋林賢著「うちなーぬ たからむん」
照屋林賢・松村洋著「なんくるぐらし」
照屋林助著・北中正和編「てるりん自伝」
カラハーイ
- 住所 /
- 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-11
- TEL /
- 098-982-7077
- 営業時間 /
- 18:00~21:00(L.O.20:30)
- HP /
- http://rinken.gr.jp/artist/rinkenband/
(りんけんバンドオフィシャルホームページ)
![]() 岡部 徳枝
岡部 徳枝



![琉球和紙の伝統を。(桑村ヒロシの島フォトコラム[第14回目])](/userfiles/images/posts/ja/thumb/2016/04/16079.jpg)