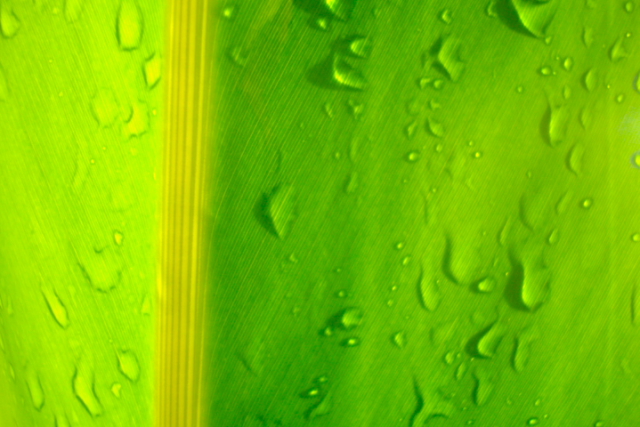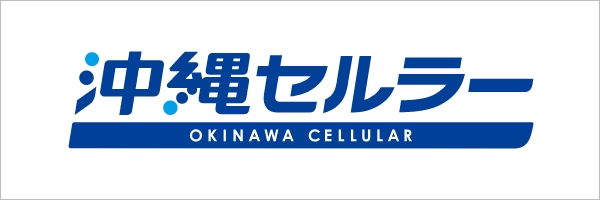ネイティヴ・オキナワンとの出会い:その1
ネイティヴ・オキナワンとの出会い:その1
Reading Material
歴史文化
初回投稿日:2015.07.23
最終更新日:2024.07.31
最終更新日:2024.07.31


~ネイティブ・オキナワンとの出会い〈その1〉~
「ヒュルルルルルルー・・・ヒュルルルルルルー・・・」。
近くの森でアカショウビンが口ずさむ牧歌的なメロディーライン。
「サッ、サッ、サッ、サ」。
隣の家から聞こえてくる暮らしの音。
朝が来れば鳥のさえずりか、隣のおばあさんが庭先を掃き清めるほうきの音で目を覚ます。

日が傾けば、喜如嘉(きじょか)の海にザブンと飛び込んで、あめんぼうのようにスーッと泳ぐ。しかるのちに、鏡のような水面に仰向けに浮びなおして、仕事でひとかきした汗を、母なる地球にサーっと流してもらう。一日の務めを果たした太陽が放つ最後の輝きと、一番星のきらめきを眺めながらの至福のひととき。
360°見渡す限り、総天然色(テクニカラー)のパノラマビュー。


集落内には赤瓦や「セメン瓦」(セメントでできた沖縄特有の薄い瓦)の古民家が多く残る。大きな葉っぱが木陰をつくるスージーグヮー(裏道)にはサンゴのかけらが敷き詰められて、満月の夜にはほのかに白く輝いている。


2001年から2003年にかけて借りていた大宜味村(おおぎみそん)喜如嘉の家には、底の方に水をたたえた井戸があり、母屋とは別にトイレとお風呂があった。
塀もヒンプンも、すいぶん昔にすぐ近くの浜から切り出されたという、板干瀬(いたびし:ビーチロックとも呼ばれる。海水中の炭酸カルシウムのセメント効果により、砂や岩石などがくっつき板状になった岩)でできているから、家にいてもほんのりと漂ってくる潮の香りを楽しめる。
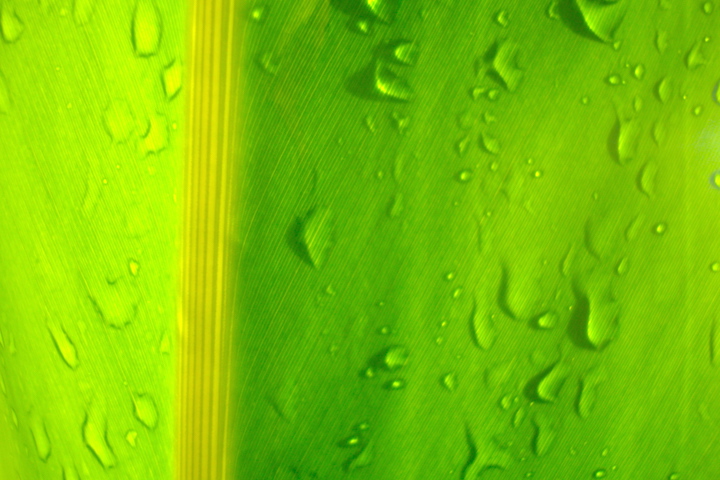
屋敷の隣は芭蕉畑。そう、伝説的な古代の一つ、芭蕉布の原料になるバナナの仲間。早起きできた朝には、黄緑色の葉っぱの上で水晶のように輝く小さな露が「おはよう」と声をかけてくれていた。沖縄に移住したてのぼくにとって、そこは文字通りパラダイス。毎日が天国の日々だった。


ものすごくプライベートな、いろいろなことが重なって、やむなくやんばるの片田舎から王府首里へと移り住んだとき、感じざるをえなかったカルチャーショック。その大きさは、初めて訪れたカルカッタ(インド)で感じた文化的な衝撃といいとこ勝負。
同じ沖縄とは思えない「都会」での生活は、東京のそれにくらべれば、じゅうぶん「南国パラダイス」ではあったものの、やんばる暮らしのあとでは、龍譚池(りゅうたんいけ)の揺らめく水面(みなも)も、弁ケ嶽(べんがたけ)の緑に萌える樹々も、色あせて見えた。
都会でのまさかの生活の毎日に心を曇らせていたとき、幸いなことに、沈んだ気持ちを明るくしてくれる人がいた。その人はうりずんのやんばるの太陽のように少しまぶしく見えた。
首里城から車で5分程度の距離にある、都会のオアシス「末吉公園」。最初にその人と出会ったのはホタル観察と肝試しで知られる緑深い公園だった。

田舎暮らしの禁断症状が出始めていたころに、友人の誘いで参加した自然体験プログラムは、せせらぎが流れる森の中をゆっくり歩き、そこに住む昆虫や鳥などの生きものと出会い、植物が見せるいろんな表情を楽しむショートトリップ。
そこでファシリテーターを務めていたのが古我知 毅(こがち・つよし)さんだった。木工作家であり、大工であり、環境教育の「先生」でもある古我知さんは当時はまだ40代後半。いまのぼくと同じくらいの年齢だ。若さが残るその笑顔は、いずれは立派な「沖縄のおじぃ」になるんだろうと思わせるのに十分だった。
雄弁というわけではないけれど、伝えるべきことを自分の言葉で丁寧に語り、ときどき思い出したように笑顔を浮かべる。
あたりまえのように風の歌を聴き、樹々の呼吸さえも感じられそうなこの人は、いったいどうやって自然を友として生きられるようになったのだろう。そういう興味を抱かせるのに十分すぎる控えめなオーラをもった人だった。
〈つづく〉
工房地球のかけら
- 住所 /
- 沖縄県八重瀬町高良338番地
- TEL /
- 090-9782-7312
![]() 沖縄CLIP編集部
沖縄CLIP編集部
同じカテゴリーの記事
よみもの検索