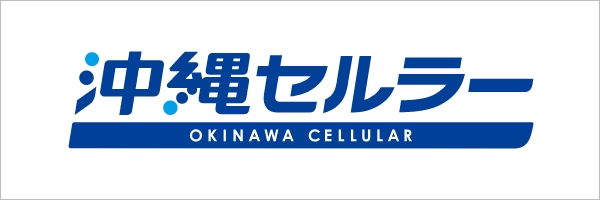紅型を媒介にして過去と未来に橋をかける人〈加治工紅型〉
紅型を媒介にして過去と未来に橋をかける人〈加治工紅型〉
Reading Material
歴史文化
初回投稿日:2018.04.18
最終更新日:2024.04.12
最終更新日:2024.04.12
「祝いごとなど、おめでたいことが起こるタイミングで購入されることが多いのが僕らが関わっている紅型です。自分たちが作ったものはいつかはお嫁に行くわけですが、嫁ぎ先で喜んでもらえている場面を思い浮かべながら仕事をしていますね。アイデアをデザインに落とし込むことに始まって、最後の仕上げまで、ひとりで制作していきます。もちろん、簡単な仕事ではありません。手間ひまがとってもかかります。でも、購入してくださった人が身に着けているところを見たりすると、苦労が一気に報われるんです」。
そう語るのは紅型職人の加治工摂(かじく・おさむ)さん。まだ37歳の若手で、2015年に独立して加治工紅型を設立。「自分が生まれ育った島の豊かさや、沖縄文化の素晴らしさを知ってもらったり、生活に取り入れてもらえたら」という思いを胸に、帯やタペストリー、うちくい(風呂敷)などを制作している。




「住んでいる家は今と昔ではずいぶん違うし、ライフスタイルもかなり変わったじゃないですか。以前だと、家紋入りのお盆やうちくいを、職人に作ってもらうのがステータスだったんですが、今ではそういうこともなくなっています。大量生産のおかげで物の値段が下がって、生活が便利になったというプラス面がありますけど、手仕事で作られたものを長く使うことの幸せは、生活が便利になった今の世の中でも確かにあると思うんですよね。僕の子ども時代がそうだったように、人の手によって生み出されたものが暮らしの中に当たり前のようにあって、沖縄のいいものに、意識しなくても触れられるような世の中になったらいいといつも思ってます」。
身にまとっているファションは「いまどき」だし、友人とシェアしているという垢抜けたアトリエで仕事をしている加治工さんだけれど、伝統への思い入れは相当強い。お父さんが八重山(やえやま)の鳩間島(はとまじま)の出身で、親戚の多くも本島に移住して暮らしていることから、何かあれば親類が集まって飲んで食べて、という沖縄らしい賑やかな時間を共有してきたことや、子どもの頃から三線や工芸品など沖縄の文化に囲まれて育ってきたことが影響しているそうだ。


「古紅型が大好きで、テレビを見てるよりも紅型の資料集を手にしている時間の方が長いと思います。それで、眺めながら思うんです。自分たちは昔の柄を“古典”って呼んで、古いもののように思っているけど、実は、それぞれが当時の最先端だったって」。中国や日本などの海外の文化とか時代の感性にインスパイアーされて、今でいえばデザイナーにあたる絵師が描き、その世界を染師が形にする。そういうふうにしてたくさんの作品が世に送り出され、その中のいくつかは時代の変化にも耐え、現在に生き残っている。それを私たちは古典と呼んでいる。
「自分が生きている今という時代からも、同じようにインスピレーションを受けてます。アメリカのポップカルチャーに影響された沖縄もその一つでしょう。だから、先人が残してきたものに対して責任を持ちながら、自分が生きている『今』から生まれてくる自分たちの紅型も追求していきたいんです」。



加治工さんの場合、沖縄の草花や生きものを作品のモチーフにすることが多いという。散歩をしている時に見た光景がヒントになることも少なくない。自分が直接見て感じたものに、頭の中の引き出しに入っている伝統柄が反応して、「これをやろう」ということになる。昔の柄をそのまま使うのことはせず、モチーフ同士のバランスや大きさ、余白などを自分なりにアレンジして、デザインするのが加治工さんの流儀だ。
たとえばツバメが飛んでいるのを目にしたとき、引き出しから出てくるのはツバメと牡丹の伝統柄という具合に。「外を歩くときは目を凝らして観察するように」。師匠の教えが身に染み付いているという。花を見るときには花の向き、葉っぱの形や反り返り方、虫食いの跡などを観察して、目に焼き付ける。自分の実体験をデザインに生かしているから生命力や躍動感に満ちた作品を作れるのだろう。


加治工さんが紅型に興味を覚えたのは大学生の頃だという。当時、バイトと遊びに明け暮れて勉強は二の次、三の次。子どもの頃から絵を描くのが好きだったこともあり、様々なイラスト・デザインを描くことで、当時頻繁に目にするようになったグラフィックアートに傾倒していた。卒業したら東京に行ってアートやデザインの仕事に就きたいと漠然と考えていた。
「国際通りにMAXっていうアパレルショップがあったんですけど、そのサインに描かれていたデザインが気になっていたんですね。あとになってそれが賀川理恵さんがデザインした紅型柄だと知ったというくらい、薄い関わりだったんですけど、ある時、沖展という美術の展示会で偶然出会った紅型作品に衝撃を受けたんです。色彩とデザインに圧倒されました」。
感動が冷めやらぬうちに、加治工さんは那覇市伝統工芸館に出かけ紅型染めの体験をした。「もっときれいにできるとはずだったのに、思い通りにいかなくて悔しかった。卒業後に何をするか明確には描けていなかったですが、この時、紅型の世界に進みたいと思いました」。


その後、伝統工芸の振興に熱心な沖縄県と琉球びんがた事業協同組合が、後継者を育成するために毎年行っている後継者育成事業に応募した。当時、男性が応募することは珍しかったが、無事選考を通過。卒業してすぐ、知念紅型研究所の知念貞男氏に師事した。
紅型は沖縄の他の伝統工芸と同様、沖縄戦で工房も作り手も押し潰され、技術が一度途絶えてしまった。戦後まもなく、壊滅状態だった紅型を復興しようと立ち上がった城間栄喜さんをはじめ、その中心にいた三宗家のひとつが、知念貞男さんの知念家だった。職人や職人希望の人の間では今でも人気が高く、なかなか入れる工房ではなかった。
「運よく入れてもらえた」という知念紅型研究所では、60代や70代のベテラン職人に混じって11年間働き続けた。仕事は思っていたより大変だった。それでも工房はアットホームな雰囲気で、仕事は厳しいながらも家族や親戚と一緒に仕事をしている感じもあったそうだ。「だから続けられた」と加治工さんは懐かしそうに振り返る。紅型の工程には、型置き、呉引き、色差し、隈取り、蒸し、糊伏せ、地染め、洗いなどがあり、後継者を育てることに熱心だった師匠は、3年おきくらいに色々な工程を任せてくれた。

「弟子入りするにあたって、10年で独立したいと話したとき、師匠は『自分で工房を構えたいのなら沖展に出展しなさい』と背中を押してくれたんです。師匠が亡くなるまで毎年出展しました。そして、師匠が亡くなった翌年の出展作品がうるま市長賞を受賞したんです」。作品のタイトルは『渡海』。モチーフは宝船と海。琉球王朝時代に中国に使節を派遣するために使われていたいう進貢船を宝船に見立て、大海原に漕ぎだす船に、お世話になった工房から独立する自分を重ねた。宝物は、師匠や先輩の教えや工房で過ごした時間や経験のメタファーだった。
「紅型の世界で一人前の職人としてチャレンジさせてもらうにあたって、感謝の気持ちを込めて、古典のリズムを自分なりにアレンジしたんです」と加治工さんは言う。リズムとは、構成とレイアウトが生み出す流れのこと。タペストリーなのか、和装の帯なのか、作品の形状や寸法によって最適なリズムを考える。平面の世界に動きと躍動感を表現できるように、自分が気持ちいいと思うリズムで絵を描いていく。
「好きな古典でも、自分にはしっくりはまらないリズムもあるんです。そういうときは、自分のリズムに整え直すんです。うきうきしてくるような世界観を表現できるように。それでも、品を損なわないように、先人に恥じないように気をつけて。紅型は王族や士族が身にまとっていたものですから、厳かさや気品は今の世でも重要です」。

2016年からは、沖縄県工芸振興センターで紅型の技術者を養成する工芸技術研修の紅型技術講師を務めてもいる。
「自分の弟子ではない人たちが対象なので、本人のやりたいことを優先しています。僕のものさしからはみ出ていたとしても、まずは組合の認定基準に収まるように伸び伸びチャレンジしてもらう。さすがに、基準からはみ出している場合には、しっかり整えるようにしています。それから重要なことはもちろん伝えるようにしてます。紅型の仕事は、今と違ってインフラも整備されてない、たいへんな時代に、先人が、おそらく命をかけてやってきたはずのもの。美術やグラフィックが好きな人にとっては、気軽に入っていきやすく見える世界かもしれませんが、琉球王朝の崩壊や沖縄戦など、いろんな苦労の積み重ねを乗り越えてきた深みのある工芸ですから。その想いを昔のことを知らない世代にもきちんと伝えられたらいいのですが…」。
「いろんな人にお世話になっているので恩返しできるように仕事を続けていきたい」と語る加治工さんには、間もなく新しく工房を構える予定がある。そこでは13mの長さの着尺(着物用の反物)を染めることができるそうだ。現在は月曜から木曜までは講師をしているため、受注品の制作で手一杯だけれど、今後は少しずつ制作の時間を増やしていくことになるはずだ。

「今みたいに電気のない時代に蝋燭の灯りで仕事をしていたような昔の職人さんだったら、自分の仕事ぶりをどう思うだろうと、時々、想像してみるんです。『これでも紅型といえるでしょうか』と、先輩に問いかけて、判断を仰ぐんです。上には上がいる世界ですからね。昔はもちろんですが、今現在もすごい先生方がたくさん活躍されています。とてもゆっくりと前に進めている気はしますが、やればやるほど先輩のすごさに気づかされます。こんなに恵まれた時代に生まれたのに、こんな自分でいいのかというのが正直なところですが、自分があの世に旅立つまでには、コツコツとですができる限り近づきたいです」。
10年後、20年後に加治工さんがどうなっているか、そして、加治工さんの教え子がどんな働きをしているか。知念貞男さんをはじめ、紅型の先輩たちは、グソー(沖縄の言葉で「あの世」のこと)で楽しみにしていることだろう。
加治工紅型
- Instagram /
- https://kajikubingata.ti-da.net/
![]() 沖縄CLIP編集部
沖縄CLIP編集部
- 前の記事 「Okinawa」の食やお酒を新しい解釈で提案するB&B+カフェ『La Passione(ラ・パッショーネ)』
- 次の記事 特別企画!沖縄の食材を使った「うまぬすぐりむん(美味しいスグレモノ)」に迫る! 黄金茶屋「いもぽき」
同じカテゴリーの記事
よみもの検索