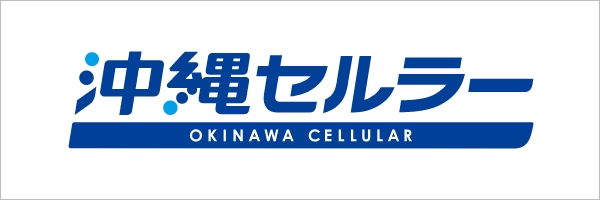背伸びをしない。無理をしない。楽しい日々から淡々と生まれる器〈茜陶房〉
背伸びをしない。無理をしない。楽しい日々から淡々と生まれる器〈茜陶房〉
Reading Material
歴史文化
初回投稿日:2018.04.11
最終更新日:2024.04.12
最終更新日:2024.04.12

陶芸王国、沖縄には個性的な陶器を作る工房がたくさんある。那覇市内の壺屋(つぼや)や本島中部の読谷村(よみたんそん)、といったメッカはもちろん、北はやんばるから南は与那国(よなぐに)まで、沖縄の島々で人の手によって、毎日、毎日、器が焼かれている。
今回訪ねたのは、浦添(うらそえ)市内の趣のある外人住宅で、独自の陶芸の世界を形にしている茜陶房の与儀祥子さんと下地かおりさんのおふたりだ。うりずんと呼ばれる初夏の沖縄は暑すぎず、風が爽やかで、その日も工房を囲む広い庭に植えられた琉球松の木漏れ日が、風に揺られてキラキラ輝いていた。
出迎えてくれたおふたりは、同じ中学と高校で過ごした幼馴染み。1997年に工房がスタートしてからは仕事のパートナーとして、仲良く仕事に取り組んでいる。「石橋を叩きすぎて割ってしまうタイプ」の几帳面で繊細な祥子さんと、「なるようになる」とどっしり構えている自由奔放なかおりさん。それぞれの長所でお互いを支え合っているように見える。
性格が違うふたりが共通して取り組んできたのは「暮らしに近いものづくり」。そんなふたりが作る器たちは、日々の暮らしで使う食器と花器が中心だ。自己主張が強すぎず、黒子のように盛り付けられるものを引き立てる。そして、どんな空間にもすーっと溶け込む順応性を持つ。それでいて、深みのある色合いや、微妙なグラデーション、優美な曲線になど、時代の変化や流行り廃りに影響されないアンティークのように、凛とした美しさも兼ね備えている。



「器の上に乗る料理とか、食べているシーンとか、そういうものを思い浮かべながら選んでもらえたら嬉しいです。食べものじゃなくてもいいんです。お花が好きな人だったらお花を乗せてもらっても楽しいでしょう」とかおりさんが切り出せば、「和食にいいかもと思って焼いたお皿を手にしたお客さんが、『スコーンに合わせるといいかも』と言ってくれたりする。
例えば焼くのが春先なら、ホタルイカと菜の花のパスタを乗っけるのにいいと思って焼いたお皿に、他の人は別のシーンを思い浮かべたりする。こういうふうに使いたい、使ってほしいと、ある特定のイメージを持って作るわけだけど、用途を限定できるわけでもないから、想像力を発揮して、それぞれの使い方を楽しんでほしい」と祥子さんが返す。
「私たちがものづくりをするときの基本的なスタンスは、器が使われるときの具体的なシチュエーションを考えること。そして、誰かをもてなしたいときに使えるものであることです。例えば、今日みたいに気持ちのいい日に、庭先にテーブルを出してそこで食事を楽しむとか。そういうシーンを思い浮かべるときには、倒れにくいデザインのグラスだったり、高低差でテーブルコーディネートにメリハリつけるのに脚付きのコンポート皿があったらいいねとか、ボウルがあればフルーツも置けるねとか考えます。記念日の時に使う器は黒っぽいシックな風合いのものがいいし、キャンドルを灯しての食事にはこんな感じのがいいとか、ストーリーから物作りが始まることが多いんです」とかおりさんは言う。



茜陶房では、それぞれの世界観をふたりが別々に形にしていくというスタイルはとらず、「こんなのを作りたいね」と2人で納得したものを力を合わせて作っているそうだ。
「作りたいと思うものは変化するし、年齢を重ねることでも変わってきてますね。若い頃に渋めの、侘び寂びの世界を追求していたけど、成熟するにつれて、カラフルできれいな色が欲しくなったり。体力のある若い時に作れてたものが作れなくなって、その代わりに、経験を積んだ今だから作れるものもある」と祥子さんはいうが、そういう変化はふたりの間でズレたり、ぶつかったりはしないのだろうか。
「作りたいものの変化も気が合うんです。バイオリズムが似てるんでしょうね」という祥子さんの言葉に、かおりさんもうんうんと頷きながら言葉を付け足す。「シチュエーションを考える時のバックグラウンドも共通項が多いんです。だから今のように一緒に作っていくスタイルに落ち着くことができたんです」。
「どちらが上司ということもなく、フラットな関係性でやってきたから、同じ年数の中でぎゅっと濃密な経験を積んだ人に比べれば、何かを成し遂げてきたようには思えない。朝起きて、作って、寝てまた起きて。『庭に出てコーヒーを飲みたい』というタイミングも同じだし、休憩ばかりで楽しいです。気分が乗ってきたらノンストップで没頭しますけど」。どちらからということもなく、ふたりの言葉はすぐに一つに重なっていく。



高校の選択課目でともに美術を選んだふたりは子どもの頃から美術の世界に進むことを夢見ていたが、高校を卒業後してからは、別々の道を進むことになった。
祥子さんは油絵専攻で東京の大学に入学。1年生の頃、木工、彫刻、陶芸、デザイン、日本画などをひと通り学ぶ機会があったという。その中で陶芸が、飛び抜けて面白かったので、学部長にお願いして、油絵専攻から陶芸専攻に変えてもらったそうだ。「旋盤木工もそうですが、くるくる回るものにのめり込むんです。回転する機械の一部に自分がなって、道具になるというか、そういう一体化する感覚が心地よかったし、それはいまでも変わらないんですが…。
油絵だと道具は何とか自分で揃えられるし、学校でなくても描くことができる。陶芸はろくろや窯が必要。大学には窯がいくつもあって、ひとり一つ使えるという恵まれた環境もあった。そういう面からもどうせ学ぶなら、陶芸の方がいいだろうと思って、陶芸を専攻することに決めました」。学生時代はひたすら作陶に没頭し、休みの日はしばしば益子や笠間など関東近県の陶芸の産地を訪ね歩いた。研修旅行で伊万里など九州全域や備前、美濃、瀬戸を訪れたし、滋賀の信楽も個人的に足を運んだ。卒業後は渋谷の陶芸教室で講師として6年ほど働いた。



その頃、かおりさんはどうしていたのだろう。
「私は高校1年生のとき、自分の美術のレベルを実感して、美大へ進学するのを諦めたんです。女子大に進学して英文学を勉強して、卒業してからは航空会社に就職しました。美術の世界から離れたからこそだと思うんですが、休みの日には美術館やギャラリーを巡って、いろんなタイプの作品を見たり、雑誌や本を通じていろんなアートに触れました。沖縄ではどうしても美術展が少ないじゃないですか。だから県外に出たいと高校の頃から思っていたし、そのチャンスが東京への進学だったんです。この学校に行ってこの勉強をしたいというより、県外に行くことが目的みたいな感じでした。開放的だし、四季もはっきりしてるし、知らない世界が広がっていて楽しかったです」。
就職してからは世界を旅するようになり、地域それぞれの魅力に触れたかおりさん。作り手として人生を過ごすことになるとは思っていなかったが、心のどこかでは、器を作りたいという思いが熾火のように残り続けていたのだろう。祥子さんより2年ほど早く沖縄にUターンして何となく過ごしていたかおりさんは、陶房を沖縄で始めたいと考えていた祥子さんから声を掛けられとき、二つ返事で誘いに乗った。
「父は大のヤチムン愛好家だったんです。新垣栄三郎さんとも交流があって、家にはヤチムンが普通にありました。陶器と磁器の違いも早くから知りましたし、高校の美術の授業で陶芸をやっていたときには、そこそこセンスがあるって思ってたんです(笑)。
そうそう、父が集めていたヤチムンには使う人を微笑ませる力がありました。たとえば、壺屋で焼かれた年代物のカップ&ソーサー。そのソーサーは少し深すぎてカップの握り手を指でつかもうとすると、指が当たって持ちにくかったんです。
それでも父はそれを愛用していて、そのカップ&ソーサーでコーヒーを飲むたびに、父は『きっとこれはコーヒーを飲んだことない人が作ったはずだ』と言って楽しそうに笑ってたんです。繰り返されるその光景を眺めるのが、私は好きだったんです。中学生の頃だったかと思いますが、私にとっての器づくりの原点はこれでした」。
これがかおりさんだとすれば、祥子さんはこうだ。「私の茶碗、私の湯のみが原点です。年明けに食器を新調する家庭に育ったんです。新しい器に毎年ワクワクしてました。弟のぶんまで私が決めてたくらいです。割れやすいから大切に扱わなくちゃという特別感のようなものがあって、大人になって、それを自分が作っていると思うと、『わーっ』って思うことがいまでも時々あるんです」。


歩んできた道は違うし、性格もまるで真反対だという祥子さんとかおりさんだが、ふたりには育ってきた環境や過ごしてき時代性や触れてきた文化など共通点がいくつかあるようだ。
「親世代のライフスタイルも似てるんです。民藝運動でも注目されたやちむんだったり、高度経済成長以降の家電製品だったり。家具も台所の風景も同じような感じだったし。私たち、キッチンを台所って呼ぶ世代なんです(笑)。ちょっと古っぽい懐かしい感じのするところとか、そういうところは私たちの作品にも反映されていますし、『こういうものを作ろうよ』というときに言葉で説明する必要もないんです」。
茜陶房の器には、1950年代を代表するデザイン様式のミッドセンチュリースタイルを彷彿させるものが多い。ちょっしたときに家族で外食に行く場所も、1950年代に創業した沖縄の老舗レストランのピザハウスや月苑飯店だったというが、占領時代に隆盛をきわめた琉米文化と呼ばれるインターナショナルな文化の影響も多分にあるのだろう。
「茜陶房を始めるにあたってどこにしようか考えたときも、この外人住宅がしっくりきたんです。懐かしい感じのする木枠の窓や、床の古びた雰囲気やシンプルで自己主張が少ない外観と佇まい。私たちの好みの空間でした」。


彼女たちが焼く茜陶房の器は、見た目で判断すれば「沖縄らしい」器でない。装飾はできる限り排除されていてシンプルだし、沖縄をイメージさせるモチーフが描かれているわけでもない。それでも、「暮らしが楽しくなるような、生活の器」であるというものづくりのスタンスや、一つ一つの器が生まれるストーリーはどこか沖縄的だし、アメリカ統治下の沖縄で生まれて、内地や外国でそれぞれの国や地域の文化の魅力に触れてきた彼女たちそのものが、もう一つの沖縄らしさともいえる。
「沖縄の赤土は厚くしないと整形しにくいし、長年の伝統を継承してきた世界ですから当然ルールもありますよね。それによその場所で陶芸を学んできた私たちが、東京から戻ってきて壺屋焼を始めるのはどこか違うと思ったし、そもそも私たちがやる必然性もないし、伝統を背負う資格もないと思ったんです」。そう語る祥子さんとかおりさんがこれからどうなっていくか、ふたりにも想像できないという。「目標を立てない。課題を決めない。できる感じ、できる形でやっていく。等身大の自分たちを受け入れてやっていきたい。できるだけ長く、おばあちゃんになっても器を作り続けたい」と祥子さんは考えている。
「世の中いろんなことがありますよね。嫌だなーと思うこともたくさんある。楽しくないことは目につきやすい。だからこそ、楽しいことは努力して探さなきゃと思うんです。楽しいことを発信していると、『ああ自分は幸せなんだ』と良い意味で騙すことができる。毎日の暮らしが楽しいというのがいちばんです。器作りもそういう思いでやっています」とかおりさんはさらりと語る。
言い残したことはないですかと尋ねたら、ふたりからそういう答が返ってきた。彼女たちが最後に残した言葉もまた、とても沖縄らしいと思った。
茜陶房
- 住所 /
- 沖縄県浦添市城間4-34-3
- 電話 /
- 098-876-5453
- サイト /
- http://akanepottery.com
- Instagram /
- https://instagram.com/akanepottery
![]() 沖縄CLIP編集部
沖縄CLIP編集部
- 前の記事 特別企画!沖縄の食材を使った「うまぬすぐりむん(美味しいスグレモノ)」に迫る! 黄金茶屋「いもぽき」
- 次の記事 やちむん体験なら「『育陶園』に行くとーええんじゃない」的 Myチャレンジング・レポ
同じカテゴリーの記事
よみもの検索