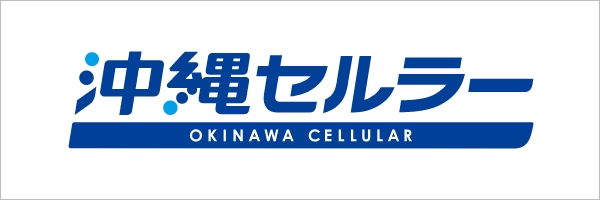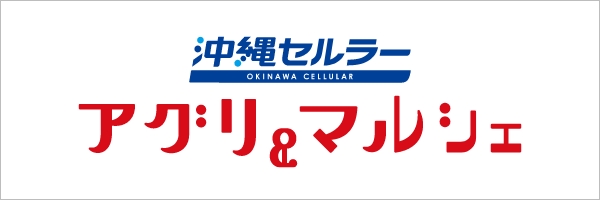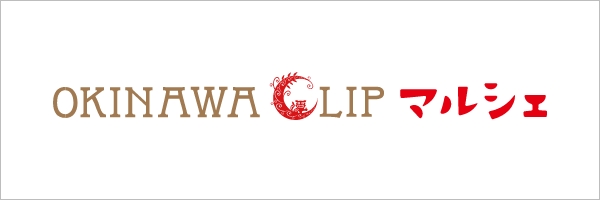かわいい子には旅をさせろ。それも、気のおけない仲間を道連れに。
かわいい子には旅をさせろ。それも、気のおけない仲間を道連れに。
Reading Material
歴史文化
初回投稿日:2016.07.27
最終更新日:2024.04.12
最終更新日:2024.04.12
「旅は道連れ世は情け」。江戸時代を思わせるこの諺は、普通に暮らしていると耳にする機会がまったくない。けれどもこの言葉が心に浮かぶことがごく稀にあったりする。今と違って、昔の旅は命がけだったのだろう。そんな時、道中を共にしてくれる仲間がいてくれたら心強かったことは今を生きる僕らにも容易に想像はつく。


旅と同じように、普段の生活でも、仲間と助けあったり、初めて会う人にも友だちのように接したりと、「お互いに思いやって、助け合って生きていこうよ」というのがこの諺が伝えたい大切なメッセージのようだ。

ご存知のように沖縄には、仲間の仕事を順番にみんなで手伝っていく「ゆいまーる」という習慣や、他人でも一度心を通わせたら兄弟と同じという「いちゃりばちょーでー」という言葉がある。そのことからもわかるように、沖縄では人と人の結びつきがお金やメンツよりも重んじられることが極めて多いといわれている。


さて、レギュラーで関わらせていただいている仕事の一つにメイドイン沖縄の雑誌『porte』がある。沖縄に生まれ育ったローカルの視点で、今が旬のお店だったり、昔からある沖縄らしいお店だったり、こだわったものづくりをしている人だったり、そういうお店や人を紹介する地元で人気の季刊誌だ。

この仕事にぼくはライターとして参加させてもらっていて、取材先に出かける時は、編集長のマキシさんとフォトグラファーのChotaroさんといつも一緒。文字通り、北へ南へと取材に出かける男3人の三羽烏といった感じなのだ。

好きな音楽も、好きな食べ物も、好きな女性も、3人3様。たまには、好みが一致する時もあるのだけれど、たいていは「絶妙に」ずれていて、それぞれの違いをそれぞれが楽しむことになったりする。

社会に出てからずいぶん経つけれど、決まったメンバーでつるむことが最近めっきり少なくなった。趣味の波乗りも一人で行くし、休みの日は彼女と二人で過ごすことが多いから、男同士で同じ時間を過ごすことあまりない。うん、数ヶ月に一度くらいは、沖縄クリップの編集部とフォトライターのメンズ飲み会というのがあったりはする。

そういう風に生活しているので、porteの仕事は高校時代に戻ったみたいでどこか懐かしくて、どこか汗臭くて、どこか甘酸っぱい。仕事には真面目に取り組むけれども、授業を抜け出して街に繰り出したような感じがして、胸がザワザワしたりする。

沖縄には山学校という言葉がある。田舎だと校舎は山・川・野原。学校をさぼって通っていた「もう一つの学校」ということらしく、那覇あたりだと、校舎は街なかの喫茶店とか、ファッションビルとか公園だったりする。先生は自然や街そのもの。友人とのフラットな人間関係からいろんなことを学べたと先輩方は嬉しそうに思い出を語ってくれる。

porteの仕事は山学校のようなものとも言える。宜野座村(ぎのざそん)で昔ながらのやり方で黒砂糖を作っている小さな工房、宜野湾市(ぎのわんし)でスタイリッシュな生活道具を作っているメタル屋さん、宮古島でやさしい味のするパンを焼く職人、八重山(やえやま)の心地よい環境のもと、自然や人と向き合って生きている人。魅力的な生き方をしている人を取材することを通して、多くのことを学び直しているのかもしれない。

いくつになっても、学びは常に目の前にあり続けるし、人との密な関わりは、背骨のようになくてはならない何か大切なものを成長させてくれるのだ。かわいい子には旅をさせろ。それも、気のおけない仲間を道連れに。そんな声がどこからともなく聞こえてきそうな三羽烏の取材の旅はこれからもぼくの喜びであり続けるだろう。
![]() 沖縄CLIP編集部
沖縄CLIP編集部
同じカテゴリーの記事
よみもの検索


![気まぐれ連載[離島クロッキー]第二回… 伊江島に残りし、my before 沖縄](/userfiles/images/posts/ja/thumb/2015/08/11876.jpg)