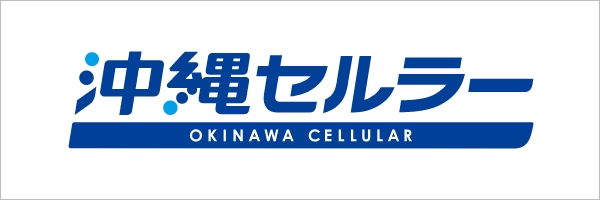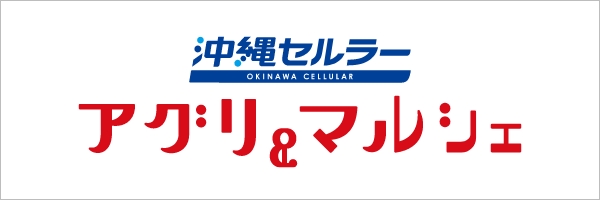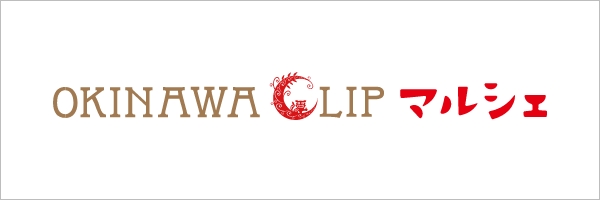【難読地名シリーズその1】難読地名、コレ読める!?(南部編)
【難読地名シリーズその1】難読地名、コレ読める!?(南部編)
Reading Material
歴史文化
初回投稿日:2016.06.29
最終更新日:2024.09.13
最終更新日:2024.09.13
ドライブの途中で見かける標識や看板。沖繩には、摩訶不思議な難読地名がいっぱい。今回は、私の地元、本島南部編をご紹介します!

南城(なんじょう)市にあるこの集落。「手登根」と書いて「てどこん」と読みます。なんだか、ウルトラマンに出てくる怪獣を思わせるようなユニークな響き。糸満(いとまん)市には「阿波根(あはごん)」という地名もありますよ。

沖繩の方言で、坂のことを“びら”または“ひら”、“ふぃら”といいます。ですから、こちらは「新里坂」と書いて「しんざとびら」。古事記に、出雲の『黄泉比良坂(よもつひらさか)』という地名が出てくるそうです。坂を表す「ひら」「さか」の2つが入っていて興味深いですね。沖繩の方言は、日本の古語とも結びつきが深いといわれますから、なんだかロマンを感じます。

さて、南城市玉城(たまぐすく)を旅した方なら、きっとこの清々しい湧き水に見覚えがあるのではないでしょうか?

「仲村渠」と書いて「なかんだかり」。国の重要文化材にも指定されている「仲村渠樋川(なかんだかりひーじゃー)」です。

続いて、南部では有名な昔からの地元御用達ビーチです! 沖繩の方言では、“新”しいを“みー”むん。“原”を“ばる”や“ばら”といいます。もうおわかりですよね。

そう!「新原(みーばる)」が正解です。

車で渡ることができる「奥武島(おうじま)」。沖繩風天ぷらのお店は行列ができるほどの人気です。毎年、旧暦の五月四日には、豊漁や航海安全を祈願するハーリー行事が行われます。こちらはその時に使われるサバニとよばれる伝統漁船です。

島の入り口の橋の上にも、かわいらしいサバニがのっかっています。

こちらは、南城市のお隣の八重瀬(やえせ)町。「具志頭」と書いて「ぐしちゃん」。「ぐしかみ」ともいいますが、地元では方言の「ぐしちゃん」読みが根強く受け継がれています。本島北部の「国頭(くにがみ)」を方言で「くんじゃん」といいますが、どこか似ている気がしますね。

南風原(はえばる)町にある「喜屋武(きゃん)」集落です。方言では「ちゃん」というのだそうです。

先ほどの八重瀬町にある「東風平」。「こちんだ」と読みます。古語にも登場する東風“こち”や、南風“はえ”は沖繩の地名に残っているのも不思議ですね。

さて、こちらは沖繩の難読地名フリークの方には有名な豊見城(とみぐすく)市にあるバス停というか地名です。「保栄茂」と書いて・・・。

「保栄茂」と書いて「びん」と読みます。その昔、この地域は“ぼえむ”または“びん”と呼ばれていたという言い伝えがあるそうです。漢字表記については、その当て字(ぼえむ〜ほえも)によって現在のようになったという説があるそうです。両方の呼び方を尊重し、残していくために「びん」という呼び方をしているそうです。

でも、なぜ「びん」といわれるようになったんだろう? かつての王国時代、琉球との交易が盛んだった中国の福建省のことを、「閩(びん)」とよんだそうです。もしかしたら、何か関係があるのではないかしら? なんて風に不思議な地名に思いを馳せながら、沖繩を巡るのもまた楽しいものです。
![]() 沖縄CLIP編集部
沖縄CLIP編集部
同じカテゴリーの記事
よみもの検索