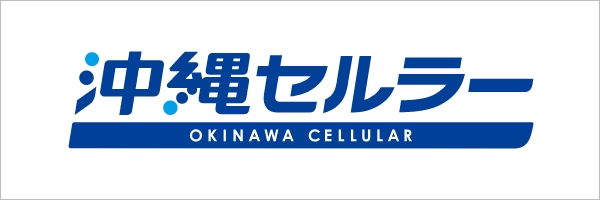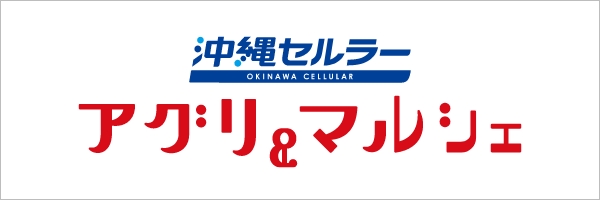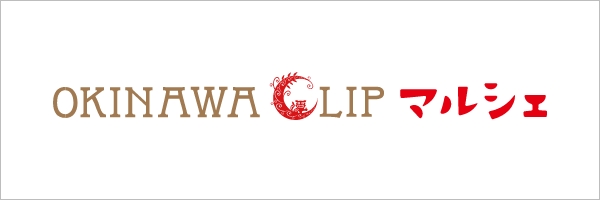“残したい沖縄”を映像で記録し伝える「海燕社(かいえんしゃ)」
“残したい沖縄”を映像で記録し伝える「海燕社(かいえんしゃ)」
Reading Material
歴史文化
初回投稿日:2025.04.10
最終更新日:2025.04.09
最終更新日:2025.04.09
映画「イザイホウ」Ⓒ海燕社
目次
海燕社の原点となった「イザイホウ」
沖縄には、古くから大切に受け継がれてきた行事や祭事、芸能や工芸などがあります。映像製作会社「海燕社(かいえんしゃ)」は、そうした中でも少しずつ消え去ろうとしている伝承文化に目を向け、“残したい沖縄”をテーマに映像で記録し、伝える活動を行っています。
「海燕社」は、これまでに自主製作映画4作品を発表。そのほか、沖縄県内の市町村から受注した地域の行事や芸能など、伝承文化の記録映像を数多く製作してきました。本記事では、「海燕社」の代表で、映像ディレクターの城間(しろま)あさみさんにインタビュー。自主製作映画のエピソードや、「海燕社」の軌跡についてお聞きしました。
![「海燕社」事務所にて、城間あさみさん]()
「海燕社」事務所にて、城間あさみさん
「『海燕社』の原点は、『イザイホウ』です」。城間さんがそう語るように、海燕社の活動の起源は、1966年製作のドキュメンタリー映画「イザイホウ」にあります。監督を務めたのは、「海燕社」の生みの親で、2020年に87歳で逝去された野村岳也(がくや)さん。
「イザイホウ」とは、沖縄県南城市(なんじょうし)の久高島(くだかじま)で12年に一度、午(うま)年に執り行われてきた秘祭のこと。久高島に生まれ育った30歳から41歳の女性が神(神職者)になる通過儀礼で、旧暦11月15日から5日間の本祭を中心に約1ヶ月かけて行われる島最大の神事です。「イザイホウ」は、1978年を最後に途絶えてしまいましたが、その前に行われた1966年の様子を撮影し、ドキュメンタリー映画として記録に残したのが野村岳也監督でした。
![映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社]()
映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社
「海燕社」は、これまでに自主製作映画4作品を発表。そのほか、沖縄県内の市町村から受注した地域の行事や芸能など、伝承文化の記録映像を数多く製作してきました。本記事では、「海燕社」の代表で、映像ディレクターの城間(しろま)あさみさんにインタビュー。自主製作映画のエピソードや、「海燕社」の軌跡についてお聞きしました。

「海燕社」事務所にて、城間あさみさん
「『海燕社』の原点は、『イザイホウ』です」。城間さんがそう語るように、海燕社の活動の起源は、1966年製作のドキュメンタリー映画「イザイホウ」にあります。監督を務めたのは、「海燕社」の生みの親で、2020年に87歳で逝去された野村岳也(がくや)さん。
「イザイホウ」とは、沖縄県南城市(なんじょうし)の久高島(くだかじま)で12年に一度、午(うま)年に執り行われてきた秘祭のこと。久高島に生まれ育った30歳から41歳の女性が神(神職者)になる通過儀礼で、旧暦11月15日から5日間の本祭を中心に約1ヶ月かけて行われる島最大の神事です。「イザイホウ」は、1978年を最後に途絶えてしまいましたが、その前に行われた1966年の様子を撮影し、ドキュメンタリー映画として記録に残したのが野村岳也監督でした。

映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社
父親が戦死した沖縄の地を訪ねて
野村さんは、石川県能登半島の出身。初めて沖縄を訪れたのは、大学卒業後、東京で映像製作会社に勤めていたころ。1965年、沖縄がアメリカの統治下にあった時代のことです。
「野村さんのお父様、宜岳(せんがく)さんはお医者様で、沖縄戦のとき軍医として出征し、戦死されました。野村さんは、父親が亡くなった土地を訪れてみたいという思いで沖縄を訪ね、そこで神の島・久高島の存在を知り、ふらっと立ち寄ったようです。そのとき、久高島の港で出会ったのが、『イザイホウ』でウッチガミ(掟神)を務める西銘(にしめ)シズさん。野村さんいわく、西銘シズさんは『歌うように語り、語るように歌う』。そんなふうに『イザイホウ』が翌年あることを教えてくださったようで、とても衝撃を受けたと話していました。それから東京に戻り、映像仲間と『イザイホウ』を撮影に行こうという話に。なけなしのお金をかき集めた完全自費製作。そのときの野村さんの映像プロダクション名が『海燕社』でした」
「野村さんのお父様、宜岳(せんがく)さんはお医者様で、沖縄戦のとき軍医として出征し、戦死されました。野村さんは、父親が亡くなった土地を訪れてみたいという思いで沖縄を訪ね、そこで神の島・久高島の存在を知り、ふらっと立ち寄ったようです。そのとき、久高島の港で出会ったのが、『イザイホウ』でウッチガミ(掟神)を務める西銘(にしめ)シズさん。野村さんいわく、西銘シズさんは『歌うように語り、語るように歌う』。そんなふうに『イザイホウ』が翌年あることを教えてくださったようで、とても衝撃を受けたと話していました。それから東京に戻り、映像仲間と『イザイホウ』を撮影に行こうという話に。なけなしのお金をかき集めた完全自費製作。そのときの野村さんの映像プロダクション名が『海燕社』でした」
3ヶ月の久高島滞在、そして作品の封印
1966年10月、野村さんは、映像制作の仲間2人と再び久高島へ。「イザイホウ」の本祭が行われる2ヶ月前のこと。まずは撮影もせず、島中を歩き回って出会う人に話を聞いたり、島で行われる行事に参加したり、島の風景や暮らしを知り、その中に溶け込むことから始めたそうです。
![映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社]()
映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社
「野村さんの話では、島の人たちはとてもあたたかく迎えてくださったということでした。『イザイホウ』は長い間、島の人以外に公開されていなかった秘祭ですが、最初に、最高神職ノロの補佐役であるウッチガミの西銘シズさんと出会い、撮影を許して頂いたことが大きかったと思います。映像って“ご縁”があると思うんです。撮りたくても撮れないときもあるし、ふっと撮れちゃうときもある。野村さんと久高島、イザイホウは、赤い糸で結ばれていたようなご縁があったのかなと感じます。それから、『神人(カミンチュ)たちは、この祭りが消え去ることを予感していたかもしれない』と野村さんは話していました。だから何かの形で残したかったのではないか。その上で自分たちを信頼してくれて迎え入れてくれたのではないかって」
撮影隊が久高島で過ごすこと約3ヶ月。このときの体験がいかに特別であったか、野村さんが綴った文章は、「海燕社」のホームページ内「撮影当時(コラム)」ページに掲載されています。今から60年前のできごとながら、目の前にその情景が浮かぶような生き生きとした描写は、胸に迫るものがあります。
![映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社]()
映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社
東京へ戻り、編集作業を進め、映画が完成したのは1967年。久高島へ再び渡り、試写会を開くことに。しかし、その会場には神人が一人も観に来てくれなかったそうです。「神人たちからは何も言ってこなかったけど、これは上映させたくないんだなと思った」――。野村さんは、映画「イザイホウ」の封印を決断。「海燕社」は一時解散となりました。

映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社
「野村さんの話では、島の人たちはとてもあたたかく迎えてくださったということでした。『イザイホウ』は長い間、島の人以外に公開されていなかった秘祭ですが、最初に、最高神職ノロの補佐役であるウッチガミの西銘シズさんと出会い、撮影を許して頂いたことが大きかったと思います。映像って“ご縁”があると思うんです。撮りたくても撮れないときもあるし、ふっと撮れちゃうときもある。野村さんと久高島、イザイホウは、赤い糸で結ばれていたようなご縁があったのかなと感じます。それから、『神人(カミンチュ)たちは、この祭りが消え去ることを予感していたかもしれない』と野村さんは話していました。だから何かの形で残したかったのではないか。その上で自分たちを信頼してくれて迎え入れてくれたのではないかって」
撮影隊が久高島で過ごすこと約3ヶ月。このときの体験がいかに特別であったか、野村さんが綴った文章は、「海燕社」のホームページ内「撮影当時(コラム)」ページに掲載されています。今から60年前のできごとながら、目の前にその情景が浮かぶような生き生きとした描写は、胸に迫るものがあります。

映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社
東京へ戻り、編集作業を進め、映画が完成したのは1967年。久高島へ再び渡り、試写会を開くことに。しかし、その会場には神人が一人も観に来てくれなかったそうです。「神人たちからは何も言ってこなかったけど、これは上映させたくないんだなと思った」――。野村さんは、映画「イザイホウ」の封印を決断。「海燕社」は一時解散となりました。
40年の時を経て封印を解き上映へ
1973年、野村さんは沖縄出身のカメラマンに誘われ、映像製作会社「シネマ沖縄」を設立。活動拠点を沖縄に移し、さまざまな記録映像製作に取り組みました。後に、この会社の演出部に若手の助手として入ることになったのが、城間あさみさん。入社当時、野村さんに「僕が作った映画を観る?」と声をかけられ観た、その作品こそが「イザイホウ」でした。
「フィルム棚に保管されたものを持ってきて、16ミリ映写機で見せてくださったんですけど、神事に疎い私でも胸がワサワサするっていうか、魂が揺さぶられてしまって。こんなに素晴らしい映画なのに誰にも観られず、ひっそりと置かれていることをもったいなく思いました」
![映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社]()
映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社
その後、「シネマ沖縄」の演出部を辞めた野村さんと城間さんは、同じ演出部の同僚と3人で新「海燕社」の活動をスタート。演出家3人のグループ活動を始動します。そして、遂に「イザイホウ」の封印を解くことを決断。演出部の別の同僚2人のバックアップも加わり、5人で上映に向けて動き出します。
「私自身、たくさんの人に観てほしいという思いがあって、ずっと野村さんに上映しようと話していました。野村さんも、撮影から長い時が経ち、変わっていく沖縄を見て言っていたんです。沖縄の心、祈りのための大切な祭祀が形骸化して、観光資源にされてしまっている。沖縄の文化が本質から離れていくことに警鐘を鳴らしたい。そのために『イザイホウ』の本質を観てほしいって。神人たちも亡くなってしまったから、この映画を遺言として受け渡す役目があるのかもしれないって」
![映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社]()
映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社
そして撮影から40年を経た2006年、16ミリフィルムをDVD化し、上映することに。与那原町(よなばるちょう)のカフェ、那覇市のリウボウホールで上映会を開催すると共に、DVDの販売も開始しました。その後、映画「イザイホウ」は、県内だけでなく、全国各地の映画館で上映され、大きな話題を呼ぶことに。
「私がこの作品で素晴らしいと思うのは、イザイホウの祭祀だけを学術的に撮るのではなく、島の暮らしも撮られていること。男は海へ漁に出て、女は畑で農作に励む。女たちが神女になるのは、男たちを守り、航海安全を祈るため。そういう根底にある精神性を伝えていて、神女の思い、野村さんの思いが凝縮されていると感じたんです。だから野村さんが元気なうちに、封印を解いて上映ができて、たくさんの人に観て頂けたことは本当に嬉しかったですね」
![野村岳也監督。写真/Ⓒ海燕社]()
野村岳也監督。写真/Ⓒ海燕社
「フィルム棚に保管されたものを持ってきて、16ミリ映写機で見せてくださったんですけど、神事に疎い私でも胸がワサワサするっていうか、魂が揺さぶられてしまって。こんなに素晴らしい映画なのに誰にも観られず、ひっそりと置かれていることをもったいなく思いました」

映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社
その後、「シネマ沖縄」の演出部を辞めた野村さんと城間さんは、同じ演出部の同僚と3人で新「海燕社」の活動をスタート。演出家3人のグループ活動を始動します。そして、遂に「イザイホウ」の封印を解くことを決断。演出部の別の同僚2人のバックアップも加わり、5人で上映に向けて動き出します。
「私自身、たくさんの人に観てほしいという思いがあって、ずっと野村さんに上映しようと話していました。野村さんも、撮影から長い時が経ち、変わっていく沖縄を見て言っていたんです。沖縄の心、祈りのための大切な祭祀が形骸化して、観光資源にされてしまっている。沖縄の文化が本質から離れていくことに警鐘を鳴らしたい。そのために『イザイホウ』の本質を観てほしいって。神人たちも亡くなってしまったから、この映画を遺言として受け渡す役目があるのかもしれないって」

映画「イザイホウ」写真/Ⓒ海燕社
そして撮影から40年を経た2006年、16ミリフィルムをDVD化し、上映することに。与那原町(よなばるちょう)のカフェ、那覇市のリウボウホールで上映会を開催すると共に、DVDの販売も開始しました。その後、映画「イザイホウ」は、県内だけでなく、全国各地の映画館で上映され、大きな話題を呼ぶことに。
「私がこの作品で素晴らしいと思うのは、イザイホウの祭祀だけを学術的に撮るのではなく、島の暮らしも撮られていること。男は海へ漁に出て、女は畑で農作に励む。女たちが神女になるのは、男たちを守り、航海安全を祈るため。そういう根底にある精神性を伝えていて、神女の思い、野村さんの思いが凝縮されていると感じたんです。だから野村さんが元気なうちに、封印を解いて上映ができて、たくさんの人に観て頂けたことは本当に嬉しかったですね」

野村岳也監督。写真/Ⓒ海燕社
戦中体験の証言を収めた「ふじ学徒隊」
2010年、これまでグループ活動だったものを法人化。新しい「海燕社」として、城間さんが代表となり、「株式会社海燕社」を設立。野村さん監督による短編ドキュメンタリー映画「ふじ学徒隊」の製作をスタートさせます。
「ふじ学徒隊」とは、沖縄戦で陸軍の第二野戦病院壕に配属され、豊見城(とみぐすく)と糸満(いとまん)で傷病兵の看護に当たった私立積徳(せきとく)高等女学校の学徒隊のこと。戦後66年間、「積徳学徒隊」、「積徳看護学徒隊」などと呼ばれていましたが、この映画から「ふじ学徒隊」の名称で呼ばれるように。校章が「ふじの花」であったこと、同窓会が「ふじ同窓会」として活動されていたことなどから、同名称になり、映画のタイトルにも採用されたそうです。
![映画「ふじ学徒隊」写真/Ⓒ海燕社]()
映画「ふじ学徒隊」写真/Ⓒ海燕社
「豊見城に海燕社の事務所を構えることになって、この地域の沖縄戦のことを調べているとき、積徳学徒隊のことを初めて知ったんです。学徒隊として従軍するか除隊するか調書がとられ、個人が選択できたことや、25人中22人が生きて戻ることができたという生存率の高さなど、ほかの学徒隊と違うことが多く、驚きました。でも、その存在はあまり知られておらず、だからこそ皆さんの証言を記録に残して伝えよう、と。それで、みんなでふじ同窓会の役員会に訪ねていって、4名の役員の方に映画のお話を相談したら、ぜひと快諾してくださって。数名の方が語り部として戦争体験を伝える活動をされていたので、その方たちがお話をしてくださると思っていたんですけど、この映画には、今まで語って来なかった方々も参加してくださったんです。学徒隊の皆さんは、ずっと『生き残って申し訳ない』という思いを抱えていて、戦争のことは思い出したくない、話したくなかった、と話されていました。でも、80歳をこえ、生かされた意味を想う中で、戦争を二度と起こさないためにと取材に応じてくださいました」
![映画「ふじ学徒隊」写真/Ⓒ海燕社]()
映画「ふじ学徒隊」写真/Ⓒ海燕社
インタビューには、ふじ学徒隊の10名が参加。現場では、「私たちが話したいことをすべて話したい。それを全部聞いてほしい」と話していたそう。戦後80年となる2025年、改めて平和の祈りを捧げ、貴重な証言にしかと耳を傾けたい作品です。
「ふじ学徒隊」とは、沖縄戦で陸軍の第二野戦病院壕に配属され、豊見城(とみぐすく)と糸満(いとまん)で傷病兵の看護に当たった私立積徳(せきとく)高等女学校の学徒隊のこと。戦後66年間、「積徳学徒隊」、「積徳看護学徒隊」などと呼ばれていましたが、この映画から「ふじ学徒隊」の名称で呼ばれるように。校章が「ふじの花」であったこと、同窓会が「ふじ同窓会」として活動されていたことなどから、同名称になり、映画のタイトルにも採用されたそうです。

映画「ふじ学徒隊」写真/Ⓒ海燕社
「豊見城に海燕社の事務所を構えることになって、この地域の沖縄戦のことを調べているとき、積徳学徒隊のことを初めて知ったんです。学徒隊として従軍するか除隊するか調書がとられ、個人が選択できたことや、25人中22人が生きて戻ることができたという生存率の高さなど、ほかの学徒隊と違うことが多く、驚きました。でも、その存在はあまり知られておらず、だからこそ皆さんの証言を記録に残して伝えよう、と。それで、みんなでふじ同窓会の役員会に訪ねていって、4名の役員の方に映画のお話を相談したら、ぜひと快諾してくださって。数名の方が語り部として戦争体験を伝える活動をされていたので、その方たちがお話をしてくださると思っていたんですけど、この映画には、今まで語って来なかった方々も参加してくださったんです。学徒隊の皆さんは、ずっと『生き残って申し訳ない』という思いを抱えていて、戦争のことは思い出したくない、話したくなかった、と話されていました。でも、80歳をこえ、生かされた意味を想う中で、戦争を二度と起こさないためにと取材に応じてくださいました」

映画「ふじ学徒隊」写真/Ⓒ海燕社
インタビューには、ふじ学徒隊の10名が参加。現場では、「私たちが話したいことをすべて話したい。それを全部聞いてほしい」と話していたそう。戦後80年となる2025年、改めて平和の祈りを捧げ、貴重な証言にしかと耳を傾けたい作品です。
継承を願い、製作工程を記録した「むんじゅる笠」

映画「むんじゅる笠」写真/Ⓒ海燕社
2021年製作の城間さん監督による「むんじゅる笠~瀬底島の笠~」は、本部(もとぶ)町瀬底島(せそこじま)の特産品「むんじゅる笠」の職人・大城善雄(ぜんゆう)さんの姿を追ったドキュメンタリー映画。「むんじゅる」とは、沖縄の言葉で麦わらのこと。麦と竹を用いて手編みでつくるむんじゅる笠は、日差しの強い沖縄で畑仕事には欠かせないものでした。昨今は、祭りの笠として、また琉球舞踊の雑踊り(ぞうおどり)の演目「むんじゅる」に用いる笠として、重要な存在となっています。

見惚れるほど美しいむんじゅる笠。写真/Ⓒ海燕社
「2009年に、本部町の伝承文化を記録する仕事を受注させて頂きました。その流れで、瀬底島でむんじゅる笠が作られてきた歴史を知り、野村さんと企画を立ち上げることにしました。でも、果たして職人の方がまだいらっしゃるのかどうか。調べていくうちに、琉球創作人形作家の座間味末子(ざまみすえこ)先生に教えていただいて訪ねた先が善雄さんでした。初めてむんじゅる笠を作っている場面を観て、本当に感動しました。それで本部町に企画を出すので、まだ製作できるかどうかわからないけれど、記録していいですか?とお願いして撮影を始めたんです。結果、企画は通らず予算化できなくて、でも瀬底島に職人はもう善雄さんしかいなくて、これは今撮影しておかないとって強く感じました。それで、どうにか方法を考えて映画にしますとお伝えして、撮影を続けていたんですけど、その最中に野村さんが亡くなってしまって。もう待ったなしだな、早く動かなくてはと思ってクラウドファンディングに挑戦しました。とてもありがたいことに、381名の方が応援してくださって。だからこの作品は、皆さんと一緒に作った映画、皆さんに作らせて頂いた映画なんです」

むんじゅる笠を製作中の大城善雄さん。写真/Ⓒ海燕社
この記録をもとに技が継承され、むんじゅる笠が残っていってほしい。そんな思いで、善雄さんの製作工程をすべて撮影。作業しているときのリアルな音と共に、ふくよかな手で繊細な麦を操り、美しい笠を編み上げていく善雄さんの姿が映し出されます。善雄さんは、むんじゅる笠の職人であると共に、瀬底島で唯一の男の神人(ウフシニヘー)でした。映画には、そうした善雄さんの暮らしの大切な一部である、神事を司る様子も収められています。

製作中の大城善雄さんの手元。写真/Ⓒ海燕社
「この作品には、善雄さんもご家族も瀬底区の方も全面的に協力してくださって。だからこそ神事も撮影できたと思っています。驚いたのが、撮影した中にノロさんが初めて観たという映像があって。善雄さんに『撮っていいよ』と言われて森の中を追いかけていったんですが、そこは女性のノロさんたちが立ち会わない神事過程だったので、『善雄たち、いつもこういうことしていたんだね、観られてよかったよ』と喜んでくださいました。その善雄さんも、完成したDVDを観て頂いた後、亡くなられて。ちょうど亡くなる数日前に会いに行ったんですけど、そのとき私が撮った写真がとってもいい笑顔だったんですよね。それを遺影に使って頂けました。胸がいっぱいになりました」

城間あさみさんと大城善雄さん。写真/Ⓒ海燕社
本映画のクレジットに記されている「原案:野村岳也」。城間さんは、野村さんのことを「年齢は離れているけど、仲間だった」と語ります。
「私は、野村さんの弟子とか後継者とか思われがちなんですが、お互いそういう意識はありませんでした。私がどんなに辛辣なことを言っても受け止めてくれて、なんでも意見を言い合えた。そうやって野村さんは、私を仲間にしてくれたんです」

映画「むんじゅる笠」撮影中の城間あさみさんと野村岳也さん。写真/Ⓒ海燕社
獅子へのうむい(思い)を紡ぐ物語「うむい獅子」
城間さん監督による2022年製作の「うむい獅子 -仲宗根正廣の獅子づくり-」は、沖縄で守り神として敬われている獅子にフォーカスした作品。木彫刻師で獅子工の仲宗根正廣(なかそねまさひろ)さんの獅子づくりにかける技と思い、地域の人々が獅子の存在に寄せる思い、そして作り手、担い手の継承にかける思いなどが描かれています。
「沖縄島南部に八重瀬町(やえせちょう)という地域があって、幸せなことに、海燕社では伝承祭祀の映像を記録させて頂く機会に何度も恵まれました。その中のひとつに、志多伯(したはく)の獅子舞と豊年祭の記録がありました。以来、志多伯に生まれ育った琉球芸能の実演家、神谷武史(かみやたけふみ)さんが小さな海燕社のことを気にかけてくださり、たびたび声をかけてくださって。私たちにとって恩人のような方。その神谷さんから、新しく獅子頭を製作するので記録映像を撮りませんか、と」
志多伯の守り神として祀られている神獅子は、崇敬の意味を込めて、加那志=「〜さま」を付け「獅子加那志(しーしがなし)」と呼ばれています。現在の獅子加那志は、1946年に作られたもの。ゆくゆく世代交代を迎えることを見据えて、未来の神獅子となる模型獅子を仲宗根さんが製作することになり、神谷さんから撮影のお声がかかったというわけです。
![獅子工の仲宗根正廣さん。写真/Ⓒ海燕社]()
獅子工の仲宗根正廣さん。写真/Ⓒ海燕社
「獅子頭の製作風景は、なかなか見られないもの。間近で見て、撮影できていることにとっても興奮しました(笑)。本当に私たちが撮っていいの? という緊張感と胸のワクワクと。映像製作をしていて、こういうときが一番幸せですね」
実は城間さんは、この撮影が決まる前に、一度仲宗根さんに会っていたのだとか。
「平和祈念像の原型を作られた山田真山(やまだしんざん)さんの映像作品を作りたいと、以前野村さんと動いていたことがあるんです。それで勉強のために、山田真山さんの展示会の講演イベントに参加したとき、質疑応答で発言されていたのが仲宗根さんでした。仲宗根さんは小さい頃、そうとは知らず、真山さんの平和祈念像の工房で遊んでいたようで、ご本人にもお会いした、と。その後、真山さんが獅子頭を作っていることを知って運命を感じ、自らも製作するようになった。そんなエピソードをお話されていたので、終わった後ご挨拶させて頂いたんです。真山さんとのエピソードは、映画の中でも仲宗根さんにお話頂きましたが、改めて映像は“ご縁”だなと感じましたね」
![神獅子を採寸中の仲宗根正廣さん。写真/Ⓒ海燕社]()
神獅子を採寸中の仲宗根正廣さん。写真/Ⓒ海燕社
劇中、志多伯の獅子加那志が登場するシーン。それまで仲宗根さんの獅子頭づくりを撮影してきた城間さんは、神獅子である獅子加那志が舞う姿を見て、「やっぱり神獅子は違う」と、その力を感じたそうです。
「私は、前で観ている仲宗根さんの背中越しに獅子加那志を撮影していたんですけど、そのとき、仲宗根さんが振り返って『なんか違うね』とぽろっと言ったんです。私と同じことを感じていたんだって嬉しくなったし、その言葉に獅子加那志も喜んでいるように見えました。獅子舞の本質がその一言に出ていたと思います。沖縄の獅子舞を見続け、支え続けてきた仲宗根さんだからこそ出た言葉だと思いました。胸にグッと迫る印象深いワンシーンです」
![志多伯の獅子加那志。写真/Ⓒ海燕社]()
志多伯の獅子加那志。写真/Ⓒ海燕社
海燕社では、「私たちが観たい映画を、一緒に観ませんか」という思いのもと、「海燕社の小さな映画会」と題した上映会を2014年から行っています。「海燕社」のドキュメンタリー映画を始め、「工芸や民俗文化関連の旧作など、ほかの映画館ではあまり上演する機会が少ないもの」をベースに、他制作会社の映画も上映。2025年度も沖縄県立美術館・博物館の講堂にて、5回(4・6・8・10・11月)開催されます。また、本記事で紹介した自主製作映画のDVDやパンフレットは、海燕社のホームページから購入可能です。DVDをライブラリー版(上映権付)で購入したい、自主上映会を開催したいという希望も受付中なので、ぜひお問い合わせを。
![2024年「海燕社の小さな映画会」の様子。写真/Ⓒ海燕社]()
2024年「海燕社の小さな映画会」の様子。写真/Ⓒ海燕社
沖縄の人々の暮らしを見つめ、そこに根付く文化と大切に向き合ってきた海燕社。城間さんが話してくださった「心のひだに触れる文化を拾い上げたい」というあたたかな思いと、「すべての作品に全力を注ぐ」という情熱。海燕社の“残したい沖縄”の記録は、これからも続いていきます。
※「海燕社の小さな映画会」上映スケジュール、DVD、パンフレットの購入案内、Youtubeなどはホームページよりご確認ください。
「沖縄島南部に八重瀬町(やえせちょう)という地域があって、幸せなことに、海燕社では伝承祭祀の映像を記録させて頂く機会に何度も恵まれました。その中のひとつに、志多伯(したはく)の獅子舞と豊年祭の記録がありました。以来、志多伯に生まれ育った琉球芸能の実演家、神谷武史(かみやたけふみ)さんが小さな海燕社のことを気にかけてくださり、たびたび声をかけてくださって。私たちにとって恩人のような方。その神谷さんから、新しく獅子頭を製作するので記録映像を撮りませんか、と」
志多伯の守り神として祀られている神獅子は、崇敬の意味を込めて、加那志=「〜さま」を付け「獅子加那志(しーしがなし)」と呼ばれています。現在の獅子加那志は、1946年に作られたもの。ゆくゆく世代交代を迎えることを見据えて、未来の神獅子となる模型獅子を仲宗根さんが製作することになり、神谷さんから撮影のお声がかかったというわけです。

獅子工の仲宗根正廣さん。写真/Ⓒ海燕社
「獅子頭の製作風景は、なかなか見られないもの。間近で見て、撮影できていることにとっても興奮しました(笑)。本当に私たちが撮っていいの? という緊張感と胸のワクワクと。映像製作をしていて、こういうときが一番幸せですね」
実は城間さんは、この撮影が決まる前に、一度仲宗根さんに会っていたのだとか。
「平和祈念像の原型を作られた山田真山(やまだしんざん)さんの映像作品を作りたいと、以前野村さんと動いていたことがあるんです。それで勉強のために、山田真山さんの展示会の講演イベントに参加したとき、質疑応答で発言されていたのが仲宗根さんでした。仲宗根さんは小さい頃、そうとは知らず、真山さんの平和祈念像の工房で遊んでいたようで、ご本人にもお会いした、と。その後、真山さんが獅子頭を作っていることを知って運命を感じ、自らも製作するようになった。そんなエピソードをお話されていたので、終わった後ご挨拶させて頂いたんです。真山さんとのエピソードは、映画の中でも仲宗根さんにお話頂きましたが、改めて映像は“ご縁”だなと感じましたね」

神獅子を採寸中の仲宗根正廣さん。写真/Ⓒ海燕社
劇中、志多伯の獅子加那志が登場するシーン。それまで仲宗根さんの獅子頭づくりを撮影してきた城間さんは、神獅子である獅子加那志が舞う姿を見て、「やっぱり神獅子は違う」と、その力を感じたそうです。
「私は、前で観ている仲宗根さんの背中越しに獅子加那志を撮影していたんですけど、そのとき、仲宗根さんが振り返って『なんか違うね』とぽろっと言ったんです。私と同じことを感じていたんだって嬉しくなったし、その言葉に獅子加那志も喜んでいるように見えました。獅子舞の本質がその一言に出ていたと思います。沖縄の獅子舞を見続け、支え続けてきた仲宗根さんだからこそ出た言葉だと思いました。胸にグッと迫る印象深いワンシーンです」

志多伯の獅子加那志。写真/Ⓒ海燕社
海燕社では、「私たちが観たい映画を、一緒に観ませんか」という思いのもと、「海燕社の小さな映画会」と題した上映会を2014年から行っています。「海燕社」のドキュメンタリー映画を始め、「工芸や民俗文化関連の旧作など、ほかの映画館ではあまり上演する機会が少ないもの」をベースに、他制作会社の映画も上映。2025年度も沖縄県立美術館・博物館の講堂にて、5回(4・6・8・10・11月)開催されます。また、本記事で紹介した自主製作映画のDVDやパンフレットは、海燕社のホームページから購入可能です。DVDをライブラリー版(上映権付)で購入したい、自主上映会を開催したいという希望も受付中なので、ぜひお問い合わせを。

2024年「海燕社の小さな映画会」の様子。写真/Ⓒ海燕社
沖縄の人々の暮らしを見つめ、そこに根付く文化と大切に向き合ってきた海燕社。城間さんが話してくださった「心のひだに触れる文化を拾い上げたい」というあたたかな思いと、「すべての作品に全力を注ぐ」という情熱。海燕社の“残したい沖縄”の記録は、これからも続いていきます。
※「海燕社の小さな映画会」上映スケジュール、DVD、パンフレットの購入案内、Youtubeなどはホームページよりご確認ください。
海燕社(かいえんしゃ)
- 住所 /
- 沖縄県豊見城市字名嘉地60番地 B-1
- TEL /
- 098-850-8485
- Webサイト /
- https://www.kaiensha.jp/index.html
![]() 岡部 徳枝
岡部 徳枝
同じカテゴリーの記事
よみもの検索