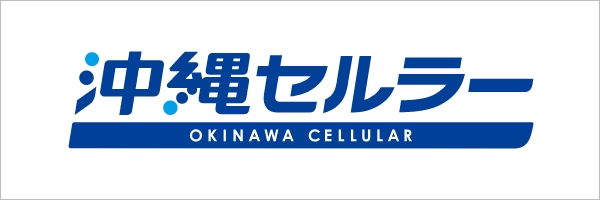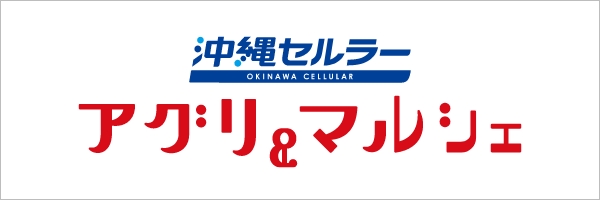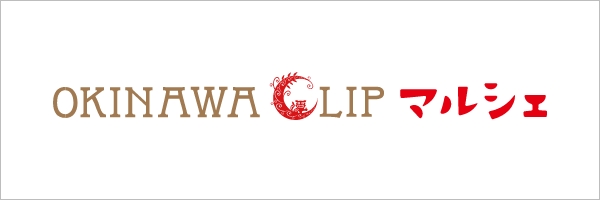酒類の世界3大コンペティション「IWSC2024」で受賞!『忠孝酒造』の軌跡(豊見城市)
酒類の世界3大コンペティション「IWSC2024」で受賞!『忠孝酒造』の軌跡(豊見城市)
Reading Material
買う
初回投稿日:2025.04.07
最終更新日:2025.04.07
最終更新日:2025.04.07
「泡盛文化の継承と創造」を基本理念に泡盛の新たな可能性を追求する忠孝酒造は、2024年にイギリスで開催された「インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション(以下:IWSC)」で、出品した泡盛4品全てで賞を獲得する快挙を成し遂げました。
目次
「蔵元」でありながら「窯元」でもある忠孝酒造

画像:忠孝酒造提供
泡盛は沖縄を代表するお酒であり、600年以上の歴史を持つ日本最古の蒸溜酒。現在沖縄県内には47の酒造所があり、それぞれが個性豊かな泡盛をつくっています。中でも豊見城市(とみぐすくし)で代々泡盛づくりを営む忠孝酒造は、泡盛の「蔵元」でありながら甕の「窯元」でもあるという唯一無二の泡盛酒造所として知られています。

毎年イギリスで開催されるIWSCは、50年以上続く歴史と欧州最大の規模を誇り世界で最も権威のある酒類コンペティションのひとつ。2024年、忠孝酒造はIWSCにはじめて出品し、出品した4品全てで賞を獲得しました。3代目で代表取締役社長の大城勤さんは「これまでいろいろと種を蒔いてきたものが目を出して、一斉に花開いた」と話します。

「忠孝甕熟成 18年古酒」は、焼酎部門において最高得点となる99点を獲得し最高金賞を受賞。「忠孝The Vanilla 14年古酒」は、最高金賞に続き焼酎部門の頂点である「トロフィー(部門最高賞)」のダブル受賞。さらに「夢航海」は金賞、「月の蒸溜所」は銀賞をそれぞれ受賞しました。その成果の裏には、これまで忠孝酒造が長い年月をかけて積み上げてきた研究と「泡盛の可能性」への強い信念がありました。
甕にこだわり味を極める

忠孝酒造が泡盛の「蔵元」でありながら泡盛の貯蔵・熟成のための甕を作る「窯元」でもあるのには、「泡盛の本質は古酒(くーす)である」という想いがあります。泡盛は熟成させることでまろやかな味わいと甘い香りを醸し出し、3年以上熟成させたものが「古酒」になります。そしてその熟成の良し悪しを左右するのが「甕」の存在です。

画像:忠孝酒造提供
大城さんは東京農業大学で醸造学を学び、卒業後は国税庁醸造研究所で「甕熟成」の研究を続けてきたという経歴の持ち主。そういった経緯もあり「よい古酒をつくるには、よい甕がないといけない」と、先代の大城繁さんは1989年に「忠孝窯(ちゅうこうがま)」を構え甕の研究をはじめました。沖縄の土をつかい試行錯誤を重ね、納得のいく「琉球城焼(りゅうきゅうぐすくやき)」の甕ができあがるまでには約3年もの時間を要したのだとか。

完成した琉球城焼の甕は、成形した時点から45%収縮し指ではじくと高い金属音を奏でます。きめの細かさと密度の高さによりお酒がもれにくく、泡盛の貯蔵・熟成に適した甕となるのです。

画像:忠孝酒造提供
今回IWSCで99点を獲得し最高金賞を受賞した「忠孝甕熟成 18年古酒」は、まさに「琉球城焼」の甕で18年の歳月をかけて生まれた古酒。甕づくりに挑戦して36年目のことでした。「我々の甕熟成をIWSCの審査員が評価してくれたことは、自信になったし名誉なこと」と大城さんは話します。
新酵母「沖縄県産マンゴー果実酵母」の発見

また泡盛の可能性を探る中で着目したのが、古酒から感じられるバニラのような“甘く豊かな香り”でした。この香りは、泡盛に含まれる「4-VG」という成分が熟成の過程で変化して「バニリン」と呼ばれる成分に変化することで生まれるもの。さらに「4-VG」は泡盛の原料であるお米の表面のフェルラ酸を酵母が食べることで生成されるということがわかっていました。
しかし従来の泡盛で生成される「4-VG」はごく少量。そこで「4-VG」をより多く生成する酵母を見つけようと、トロピカルテクノセンターと沖縄工業高等専門学校との共同研究を実施しました。沖縄の自然界に存在するあらゆる酵母の中から「4-VG」をより多く生成する酵母を探し、2007年にマンゴーの実からとれる「沖縄県産マンゴー果実酵母」を発見したのです。

そして生まれたのが、IWSCで最高金賞と部門最高賞のダブル受賞を果たした「忠孝The Vanilla 14年古酒」。時間が経つごとに香りがひらき、バニラのような芳醇(ほうじゅん)な香りをたのしむことができるこの泡盛は長年の研究の賜物であり、口当たり・風味・香り・後味などトータルで高い評価を受けました。
「泡盛文化の継承と創造」
なぜここまで泡盛への探究を続けるのか。そこには忠孝酒造の基本理念である「泡盛文化の継承と創造」という言葉があります。
![忠孝蔵 外観]()
画像:忠孝酒造提供
「泡盛文化の継承」という言葉には、黒麹菌を発見し受け継ぎ伝えてきた先人への敬意と、古酒文化を継承していくという意思が込められています。実は酒造りに黒麹菌を使うのは世界的に珍しく、現在分かっているのは泡盛や一部の焼酎のみ。先人による黒麹菌の発見と黒麹菌から蒸留酒をつくりあげる知恵と工夫がなければ、泡盛は生まれることはありませんでした。そして琉球王朝時代、客人をもてなすため振る舞われた泡盛は、貯蔵のために甕に入れて寝かせられ、それが古酒文化・甕熟成文化のはじまりとなりました。だからこそ忠孝酒造では自社で甕をつくり古酒文化を継承し「泡盛の本質は古酒である」を体現しているのです。
![泡盛の原料となる麹]()
画像:忠孝酒造提供
![泡盛の原料の麹を混ぜる作業]()
画像:忠孝酒造提供
また、既存の技術や製法にとどまることなく新たな挑戦や研究を続ける姿勢は「泡盛文化の創造」の表れです。忠孝酒造には泡盛の酒造所で唯一、博士号を取得した社員がいます。ワインや日本酒を研究し博士号を取得した人は多くいますが、実は泡盛の研究で博士号を取得した人は3名しかいませんでした。
![泡盛を確認する男性]()
画像:忠孝酒造提供
研究がないということは、進化がないということ。その状況を危惧した大城さんが「一緒に博士号をとりに行こう」と社員の熱田和史さんに呼びかけたのがきっかけです。そして2006年、忠孝酒造での「シー汁浸漬」の研究が認められ、熱田さんは醸造学博士号の取得者となったのです。研究には多くの時間がかかります。ノーベル賞を取るような研究であっても評価されるのは長い年月が経ち世界の様々な分野で応用されるようになってから。忠孝酒造が長年続けてきた研究は、IWSCでの受賞など、ここにきてようやく新たな泡盛文化の創造として花開いてきたのです。

画像:忠孝酒造提供
「泡盛文化の継承」という言葉には、黒麹菌を発見し受け継ぎ伝えてきた先人への敬意と、古酒文化を継承していくという意思が込められています。実は酒造りに黒麹菌を使うのは世界的に珍しく、現在分かっているのは泡盛や一部の焼酎のみ。先人による黒麹菌の発見と黒麹菌から蒸留酒をつくりあげる知恵と工夫がなければ、泡盛は生まれることはありませんでした。そして琉球王朝時代、客人をもてなすため振る舞われた泡盛は、貯蔵のために甕に入れて寝かせられ、それが古酒文化・甕熟成文化のはじまりとなりました。だからこそ忠孝酒造では自社で甕をつくり古酒文化を継承し「泡盛の本質は古酒である」を体現しているのです。

画像:忠孝酒造提供

画像:忠孝酒造提供
また、既存の技術や製法にとどまることなく新たな挑戦や研究を続ける姿勢は「泡盛文化の創造」の表れです。忠孝酒造には泡盛の酒造所で唯一、博士号を取得した社員がいます。ワインや日本酒を研究し博士号を取得した人は多くいますが、実は泡盛の研究で博士号を取得した人は3名しかいませんでした。

画像:忠孝酒造提供
研究がないということは、進化がないということ。その状況を危惧した大城さんが「一緒に博士号をとりに行こう」と社員の熱田和史さんに呼びかけたのがきっかけです。そして2006年、忠孝酒造での「シー汁浸漬」の研究が認められ、熱田さんは醸造学博士号の取得者となったのです。研究には多くの時間がかかります。ノーベル賞を取るような研究であっても評価されるのは長い年月が経ち世界の様々な分野で応用されるようになってから。忠孝酒造が長年続けてきた研究は、IWSCでの受賞など、ここにきてようやく新たな泡盛文化の創造として花開いてきたのです。
島の誇りから世界の誇りへ
大城さんの会話の中には「泡盛の可能性」という言葉が多く出てきます。それはまだ知られていない泡盛の可能性を伝え、その価値観を上げていきたいという想いから。大城さん自ら案内人を務める泡盛ツアー「CHUKO月あかり」は、泡盛の概念を変え泡盛の未知なる可能性との遭遇がテーマになっています。
![忠孝酒造の大城社長]()
第1部の「泡盛×五感 未知なる世界への入門」では、厳選された8種類の泡盛を「琉球城焼」のおちょこでテイスティング。自らの五感を使い、製法や技術の違いで表情を変える泡盛の官能評価を行います。第2部の「泡盛×泡盛 究極のブレンド造り」では、堪能評価の結果に基づいて8種類の泡盛をブレンド。少しのバランスの違いによる香りや味わい、印象の変化を感じながら自らの感覚を頼りに究極のブレンド造りに挑戦します。そして第3部では「泡盛×食 理想のマリアージュの探求」として、県産素材を使った料理とその魅力を引き立てる泡盛を一緒に味わいます。泡盛と料理の風味が口内で共鳴し、料理も泡盛もさらにおいしくなる。その瞬間を味わい、たのしむことができます。
独自の研究やこれらひとつひとつの取り組みを通して、泡盛の価値を上げ「“島のスピリッツから世界のスピリッツへ、島の誇りから世界の誇りへ”と繋げていきたい」と話してくれました。

第1部の「泡盛×五感 未知なる世界への入門」では、厳選された8種類の泡盛を「琉球城焼」のおちょこでテイスティング。自らの五感を使い、製法や技術の違いで表情を変える泡盛の官能評価を行います。第2部の「泡盛×泡盛 究極のブレンド造り」では、堪能評価の結果に基づいて8種類の泡盛をブレンド。少しのバランスの違いによる香りや味わい、印象の変化を感じながら自らの感覚を頼りに究極のブレンド造りに挑戦します。そして第3部では「泡盛×食 理想のマリアージュの探求」として、県産素材を使った料理とその魅力を引き立てる泡盛を一緒に味わいます。泡盛と料理の風味が口内で共鳴し、料理も泡盛もさらにおいしくなる。その瞬間を味わい、たのしむことができます。
独自の研究やこれらひとつひとつの取り組みを通して、泡盛の価値を上げ「“島のスピリッツから世界のスピリッツへ、島の誇りから世界の誇りへ”と繋げていきたい」と話してくれました。
素晴らしい文化、素晴らしい泡盛を残していくために

画像:忠孝酒造提供
醗酵学の権威である故坂口謹一郎氏は、「日本の酒」という本の中に「古い文明は必ずうるわしい酒を持つ。すぐれた文化のみが、人間の感覚を洗練し、美化し、豊富にすることができるからである。それゆえ、すぐれた酒をもつ国民は、進んだ文化の持ち主であるといっていい。」という言葉を残しています。すなわちそれは「素晴らしい文化があるところには素晴らしい酒がある」という意味。
大城さんは大学生の時にヨーロッパの各地を自転車で旅したときに、昔ながらの街並みや石畳などが大切に守られる様子に触れヨーロッパの“文化の凄さ”を感じたそう。それと同時に、沖縄の文化の特異性や素晴らしさに気付き「泡盛は琉球民族が育んだ大切なお酒だ」と改めて思ったのだそうです。
沖縄は琉球王朝時代に、諸外国との交易を通して独自の文化を育んできた場所。料理・歌・舞踊・陶器・漆器・空手。「これだけの文化を醸し出すことに、どれだけの沖縄の交易力の高さがあるかということに沖縄の人さえも気付いていないんです」

「泡盛はすごいポテンシャル(可能性)、そして文化を持っている」。
この時に感じた想いが、現在の忠孝酒造の取り組みに繋がっているのです。「文化や文明は止まったら朽ちていく。進化しないと腐って壊れていくだけ。泡盛を過去の遺産にしないためやるべき事をやっていかないと。」
那覇空港から車で10分ほどの場所にある「くぅーすの杜 忠孝蔵」は、昔ながらの手作り泡盛工場や、古酒が眠る県内最大級の木造の蔵、琉球城焼の甕を作る「忠孝窯」などを見学できる施設です。いま一度改めて泡盛の可能性を感じてみてはいかがでしょうか。
くぅーすの杜 忠孝蔵(ちゅうこうぐら)
- 住所 /
- 沖縄県豊見城市字伊良波556-2
- TEL /
- 098-851-8813
- 営業時間 /
- 9:00~17:30
- 定休日 /
- 木曜日・元旦
- Webサイト /
- http://www.chukogura.com
![]() 上村 明菜
上村 明菜
同じカテゴリーの記事
よみもの検索