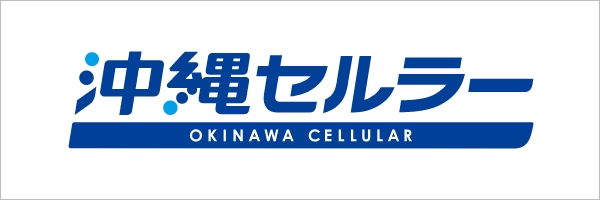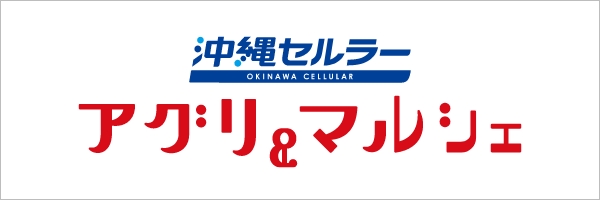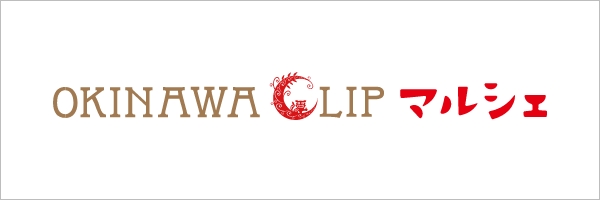琉球王国の原風景 壺屋やちむん通り
琉球王国の原風景 壺屋やちむん通り
Reading Material
あそぶ
放送日:2023.12.04 ~2023.12.08
初回投稿日:2024.01.09
最終更新日:2024.05.27
最終更新日:2024.05.27
戦前からの原風景の中で暮らす

子どものころはこの道でよく遊んだ、と育陶園六代目陶主の高江洲忠さん
国際通りに隣接する壺屋は、やちむん(焼き物)の町として知られますが、1682年、琉球王府が各地に点在していた窯場(湧田、首里宝口、知花)を壺屋に統合し、壺屋焼きとしたことが始まりです。
壺屋のメイン通り「やちむん通り」は沖縄を代表する観光スポットになっていますが、通りから一歩筋道に入ると、300年前からあるガジュマルやフクギ、アカギ、戦前からの道幅を作る石垣、石敢當、シーサーが鎮座する赤瓦の家屋など、戦火を逃れた壺屋ならではの風景が残っています。
うつわや絵画に描かれるこうした沖縄の原風景の中で生まれ育った窯元、育陶園六代目陶主の高江洲忠さんは、
「昔はこの小道が主要の道路でしたよ。繁華街とこんなに近い町の真ん中で焼き物をやっているのは、日本中を探しても壺屋ぐらいじゃないですか?」
職人たちの手仕事に触れる町
壺屋の小高い傾斜地は登り窯に適していたので、全盛期は40基もの登り窯が立ち並んでいました。戦争で暮らしに必要な道具のすべてを失った沖縄ですが、戦後の壺屋では、ご飯をよそうマカイ(茶碗)がせっせと作られました。当時の登り窯から立ち上る煙は、まるで復興ののろしのようで、人々を勇気づけました
1972年の復帰後は、人口の増加や環境に配慮して、多くの窯元が郊外の読谷村へ移り、現在の壺屋のやちむんづくりでは、ガス窯が主流になっています。
![国指定重要文化財「新垣家住宅」]()
壺屋のシンボル的なスポットの国指定重要文化財「新垣家住宅」。王朝時代から続く陶工の住宅。同じ敷地内の東ヌ窯(あがりぬかま)は上焼(釉薬をかけた焼物)の登り窯。
![南ヌ窯の登り窯]()
南ヌ窯は荒焼(釉薬をかけない焼物のこと)の登り窯
一歩裏道に入ると、もくもくとやちむんを作り続ける350年前と変わらない陶工たちの風景があります。
![やちむん制作中の職人たち]()
温度や湿度など、天候によって大きく左右されるやちむんづくり
![壺屋の伝統的な柄は線彫りという技法]()
壺屋の伝統的な柄は線彫りという技法で描かれている
1972年の復帰後は、人口の増加や環境に配慮して、多くの窯元が郊外の読谷村へ移り、現在の壺屋のやちむんづくりでは、ガス窯が主流になっています。

壺屋のシンボル的なスポットの国指定重要文化財「新垣家住宅」。王朝時代から続く陶工の住宅。同じ敷地内の東ヌ窯(あがりぬかま)は上焼(釉薬をかけた焼物)の登り窯。

南ヌ窯は荒焼(釉薬をかけない焼物のこと)の登り窯
一歩裏道に入ると、もくもくとやちむんを作り続ける350年前と変わらない陶工たちの風景があります。

温度や湿度など、天候によって大きく左右されるやちむんづくり

壺屋の伝統的な柄は線彫りという技法で描かれている
暮らしに根付く祈りの文化
壺屋には、人間は自然の中で生かされていることに気づかせてくれる魅力的なスポットがたくさんあります。旧暦の朝、町の人々は壺屋公民館にある拝所、ビンジュルグワーをスタートして、登り窯やカー(井戸)を巡り、手を合わせます。この祈りの行事には、壺屋に暮らしている人なら誰もが参加できます。
![大きなガジュマルに見守られている「ビンジュルグヮー」]()
大きなガジュマルに見守られている「ビンジュルグヮー」は壺屋発祥の場所。きれいな水源があり、地域の人たちに神聖に保たれている。
![登り窯に祈る高江洲さん]()
高江洲さんは「登り窯に火を入れる前は、お酒と塩を置いて、まがしそーれ(いい子どもを産ませてください)とみんなで祈りましたよ」といいます。

大きなガジュマルに見守られている「ビンジュルグヮー」は壺屋発祥の場所。きれいな水源があり、地域の人たちに神聖に保たれている。

高江洲さんは「登り窯に火を入れる前は、お酒と塩を置いて、まがしそーれ(いい子どもを産ませてください)とみんなで祈りましたよ」といいます。
原風景だから守られている壺屋のじんじん

壺屋じんじんクラブ提供の観察会のようす
戦前からの土や石垣が残る壺屋のもう一つの魅力はじんじん(ホタル)が生息していること。石垣に卵を産む沖縄の陸ボタルが観察できる那覇の数少ないスポット。壺屋のじんじんは、沖縄のわらべうたにも登場します。地元の団体「壺屋じんじんクラブ」では、地元の人たちと協力しながら、観察会でホタルの生態を学び、保全活動を行っています。
町と文化を継承する若者たち
県内外、海外からのお客さんで賑わうやちむん通りには、伝統的な力強い作品や新しい感性でものづくりをするお店が立ち並んでいます。
現在やちむん通り会の会長を務める、うちなー茶屋ぶくぶくの店主、島袋弘貴さんと、副会長で育陶園の社長を務める高江洲若菜さんは、「壺屋という先人たちから受け継いできた景色の中で、職人の手仕事で作るやちむんを盛り上げていきたい。仲間とともに、沖縄の景色を繋いでいきたいですね」と話してくれました。
![観光客が行き交うやちむん通り]()
世界中からさまざまな人が集まるやちむん通り
![うちなー茶屋ぶくぶくの店主、島袋弘貴さん]()
うちなー茶屋ぶくぶくの店主、島袋弘貴さん
![育陶園の社長を務める高江洲若菜さん]() この地で生まれ育った育陶園の社長を務める高江洲若菜さんにとって、壺屋はいつまでも残していきたいかけがえのない場所。
この地で生まれ育った育陶園の社長を務める高江洲若菜さんにとって、壺屋はいつまでも残していきたいかけがえのない場所。
現在やちむん通り会の会長を務める、うちなー茶屋ぶくぶくの店主、島袋弘貴さんと、副会長で育陶園の社長を務める高江洲若菜さんは、「壺屋という先人たちから受け継いできた景色の中で、職人の手仕事で作るやちむんを盛り上げていきたい。仲間とともに、沖縄の景色を繋いでいきたいですね」と話してくれました。

世界中からさまざまな人が集まるやちむん通り

うちなー茶屋ぶくぶくの店主、島袋弘貴さん
 この地で生まれ育った育陶園の社長を務める高江洲若菜さんにとって、壺屋はいつまでも残していきたいかけがえのない場所。
この地で生まれ育った育陶園の社長を務める高江洲若菜さんにとって、壺屋はいつまでも残していきたいかけがえのない場所。壺屋やちむん通り
- 住所 /
- 沖縄県那覇市壺屋1丁目16
![]() 沖縄CLIP編集部
沖縄CLIP編集部
TVアーカイブ配信中
放送日:2023.12.04 ~ 2023.12.08
-
放送日:2023.12.04
-
放送日:2023.12.05
-
放送日:2023.12.06
-
放送日:2023.12.07
-
放送日:2023.12.08
同じカテゴリーの記事
よみもの検索